体は暑くないのに、手のひらや足の裏が湿っていることが多く、時にはべたつくほどになることを悩みに思っている人がいます。
掌に汗をかきやすい人は手掌多汗症、足の裏に汗を書きやすい人は足底多汗症という名前がついていて皮膚科で治療が可能です。
治療するほどではなくても自分ではべたついていると悩んでいる人もいるでしょう。
また、大事なプレゼン前や緊張するシーンでは手汗をかくことを経験したことがある人もいるかと思います。

緊張やストレスなどにより交感神経が優位になると手の汗腺を刺激して、暑くなくても汗をかくと言われています。
ですが、緊張しなくても手や足がべたつくことが多いと感じている場合は、中医学の考え方を基本に生活や食事を変えると解決できる可能性があります。
目次
汗をかく場所で分類できる五臓の弱り
中医学(中国伝統医学)では、体の各部位と五臓を体系立て考えられて来ました。
五臓の肺と関わるのは、大腸、鼻、皮膚、腎と関わるのは、膀胱、耳、骨、髪という具合です。
この中でどこに汗をかくのかも五臓のどこに弱りがあるかのヒントになります。
掌や足の裏が緊張やストレスを感じていない時でもべたつく傾向がある場合は、五臓の脾の弱りを考えましょう。
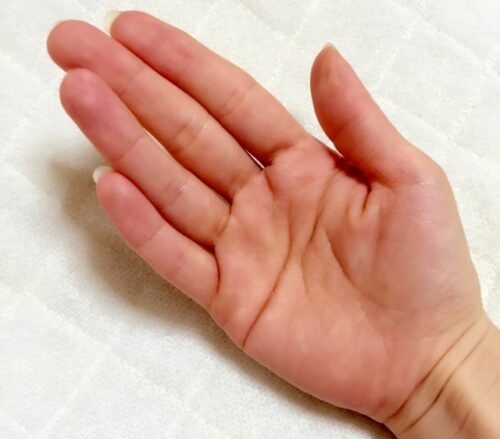
脾とは消化器系のシステムです。
脾が弱ると余分な水分を溜めやすくなり、そこに過食・揚げ物・多量の飲酒などの条件が重なると不要な水分が熱化され湿熱という熱を生むようになるのです。
その結果、体は暑く感じていなくても掌や足の裏が常にしっとり、べたつくという状態になりやすいです。
このような体質の人が、緊張やストレスにさらされたり自分では意識していなくても交感神経優位の状態が続いていたりすると、より手足に汗をかきやすい状態になると考えられます。
手足に汗をかく人とかかない人を比べた場合、かく人はかかない人よりも体に不要な水分を溜めている可能性がある訳です。
赤ちゃんや幼児は大人に比べて手足はしっとりしています。
不要な水分を溜めているというより、子供は陰陽の陽の塊なので(大人より体温が高い)、体に熱がこもりやすいためこれを冷ます水分を貯めていると考えられます。
中医学で考える手足の汗対策方法とお勧めの食べ物
中医学で考える手足の汗をかきにくくする方法は、不要なものは出し溜めにくくする。溜める原因となるものを止めるということになります。
ただし、残念ながら、手足の汗をかきにくくするために「これだけすれば!」とか「これさえ食べれば!」という特効薬的なものはありません。
皮膚科の治療方法は薬物療法、イオン導入法(イオントフォレーシス)、ボトックス注射、神経ブロック等があるようです。
中医学では、原因が脾の弱り(もともとの体質的なものもある)から不要な水分を溜めているとことを基本に、交感神経が優位の状態になりがちではないか?と考えます。
私自身、幼いころに胃腸が弱く、手を繋いで欲しい時に「べとべとするから」と断られた幼いころの記憶があります。

胃腸が弱い体質と何十年も付き合って来たことと中医学や薬膳の知識があるので、今では手足がべたつくことは滅多にありません。
手足の汗をかきにくくする方法の、「不要なものは出し溜めにくくする。」「溜める原因となるものを止める。」これを具体的に言うと次のようになります。
1.今溜めている不要な水分を尿で出す。
2.脾を弱らせると不要な水分を溜めやすくするため、脾を弱らせる飲食を控える。
3.脾を丈夫にすることを心がける。
4.ストレスを発散したり極度の緊張を和らげる。
ということになります。
1.今溜めている不要な水分を尿で出す
中医学を基にする薬膳で考えると、今溜めている不要な水分を排泄する方法は、尿で出すのが一番です。
排泄するためにおすすめする食材は、
海藻類・雑穀類・瓜類・小豆・緑豆(緑豆もやし)・黒豆などの豆類全般・はと麦・とうもろこしのひげ・などがあります。

蒸し暑い香港や台湾の夏のデザートにははと麦や緑豆を使ったものが多いです。これは薬膳が食生活に沁み込んでいるからでしょう。
ここで注意して欲しいことは、きゅうりやゴーヤなどの瓜類は体にこもる熱を冷ます性質があるということ。
要らない水分を溜めていて足が浮腫み冷える人は生で食べずに調理して食べるか体を温める性質を持つ食材と合わせて冷えの影響を緩和させましょう。
これが私がお伝えしている「なかったことにする薬膳」です。
2.脾を弱らせると不要な水分を溜めやすくするため、脾を弱らせる飲食を控える。
脾は湿気と冷えに弱いという特徴があります。
弱ると余分な水分を溜めやすくなり水はけが悪くなるため、通常なら排泄できる不要な水分を溜めやすくなってしまうのです。
ですから、脾を弱らせる行為をなるべく止めることで手汗の予防ができるのです。
脾を弱らせる飲食とは、
・冷たい飲み物食べ物・・・アイスクリームやキンキンに冷えた飲み物
・脂っこい食べ物・・・天ぷら・から揚げ・とんかつ・脂の多い肉・マグロのトロ・養殖うなぎなど
・砂糖を使った甘い食べ物・飲み物・・・ケーキ類・菓子パン類・甘いお菓子類・ジャム・甘いチョコレートなど
・コッテリした味付けの物・・・ご飯が進む味つけですね。
二つ目から四つ目までを合わせて肥甘厚味(ひかんこうみ)と言います。
脾を弱らせるのは冷飲食と肥甘厚味の食べ物飲み物です。

胃腸が弱っている時でなければ一回くらい食べたり飲んだりしても特に変化はないと思いますが、一年中アイスコーヒーを飲んだりコッテリ脂っこい食事が日常だったりすると脾が弱り要らない水分を溜める可能性が高くなってしまいます。
手足の汗を予防するには、このような食生活を避けることですね。
冷たい水を一度に何リットルも飲み、脂っこくコッテリした味付けの食事を食べ続けたら良くないのはイメージしやすいでしょう。
不要な水分を溜めることは言い変えると脂肪を溜めるとも言えます。中医学で皮下脂肪、水太りは要らない水分が原因と考えられるのです。
3.脾を丈夫にすることを心がける。
脾の弱点がわかったので、冷たいものや肥甘厚味を控えるということだけでも脾を弱らせない生活に近づけるでしょう。
ですが、もう一歩進んで脾を丈夫にしておくと多少冷たいものを摂っても肥甘厚味を食べても脾が弱りにくくなりますね。
脾を丈夫にするためのおすすめは、
・天然のほっこりした甘みのあるもの・・・米・芋類・豆類・かぼちゃ・とうもろこしと白身魚・鶏の胸肉等
これらを温かい状態でよく噛んで食べることです。
「よく噛んで」は現代人が忘れがちなこと。
やはり食事の基本はよく噛むことですね。
唾液の消化酵素を食べ物によく混ぜてから胃腸に送れば消化器系はハードワークにならない訳です。
日頃から消化器系を労わっていることが手足の汗予防になりますね。
4.ストレスを発散したり極度の緊張を和らげる。
適度な緊張は良い刺激となって必要なものです。
中医学では何事もバランスが大事と言います。
働きすぎも、だらけ過ぎも良くないというように、緊張と弛緩(リラックス)もバランスなのです。
真面目なタイプは緊張しやすいとも言われます。
きちんとしなきゃと常に思ってしまうからでしょう。
けれど、過度のストレスや緊張は交感神経優位状態が続いていることになり、手汗の原因になってしまいます。
緊張やストレスを常に感じる生活を少しでも変えるために中医学では「気」を巡らせます。
「気」とは体の構成要素「気・血・津液」の一つで、エネルギーや生命力であり、その人の体の状態を整え、血や津液を巡らせたり体のバリア機能を保つ働きがあります。
「気」が体の中を巡っていることで血巡りも水巡りも正常であると考えられています。
ストレスや緊張が続くと「気」の巡りが滞ってしまい「気」によって運ばれる水の巡りも正常ではなくなってしまうために、本来なら尿として体の外に出るはずが体に溜まりやすくなるということなのです。
「気」を巡らせるためには香りを使うのがおすすめです。
良い香りと感じるものが「気」を巡らせるからです。
食材で言えば、香味野菜・ハーブ類・柑橘系のフルーツ・出汁の香り等。花の香りやアロマテラピーで使われる精油など。
かつお出汁の香りは日本人のDNAに刻まれているのではないかと感じます。
出汁の香りで癒される人が少なくないのも頷けます。
かつお節の香りの成分には、副交感神経を優位にさせ心身をリラックスさせる効果があると言われています。
昨今の日本の家庭では洋食が中心となり、味噌汁離れが進んでいます。
みそ汁を作っても子供が食べないので作らなくなったとか、みそ汁はおかずにならない等の理由があるようです。
リラックスのためにもひいては手足や足汗の予防のためにも出汁をひいたみそ汁を飲みたいですね。

香りの他には、軽い運動やぬるめのお風呂に入ることもおすすめです。
激しい運動は交感神経優位状態にしますが、ヨガやラジオ体操、散歩などは気を巡らせるのに最適な運動と言えるでしょう。
お風呂は39℃~40℃程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かります。
42℃以上の熱いお湯は交感神経優位になるのでご注意くださいね。
手足に汗をかきやすい人の特徴と食べ物で実践する対策のまとめ
ここまで解説してましたが、手足に汗をかきやすいのは汗の出る部位から五臓の脾が弱っているか、もともと脾が弱く要らない水分を溜めている可能性があります。
そして、ストレスや緊張を感じやすいと特徴もあります。
手足の汗をかきにくくするためには、脾を弱らせる食生活を止めて脾を労わり丈夫にしておくことです。
要らない水分を溜めにくく交感神経優位状態を長く続けないためにも香りや軽い運動・ぬるめの入浴などで気を巡らせてリラックスすることも大切です。
【関連記事】






