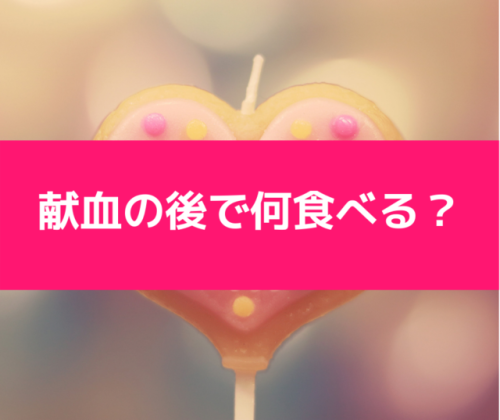
コロナ禍になり緊急事態宣言が発令、外出機会が減ったことで献血する人が減少しているそうです。
コロナ以外の病気により手術が必要な人や、大けがなどの大量出血のために輸血が必要な時は献血による血液バンクの存在はとても大切ですよね。
機会があれば献血してみようという人、献血すると自分が疲れてしまうからとしり込みする人、いろいろだとは思います。
機会があれば献血したい人も献血すると自分が疲れてしまうという人も、献血した後の食べ物がとても大切です。
献血後には何を食べたら良いのでしょうか?
薬膳では、補血と言って体の構成要素「気・血・津液」のうち血を作る食べ物を食べると良いと考えます。
目次
献血の後は失った血を作る食事
血(けつ)を補う食べ物は、色で覚えると分かりやすいです。
血の色の赤いもの、黒いもの(血は固まると黒くなる)、ポパイのほうれん草の緑の濃いもの。
まずはこの三色の食べ物を使った食事だと思ってください。色ごとにあげてみますね。
【赤いもの】
にんじん、ビーツ、牛肉の赤身、レバー(鶏・豚)、マグロ、カツオ、タコ、赤貝、なつめ、クコの実、ライチなど
【黒いもの】
黒豆、黒ごま、黒きくらげ、カシス、ブルーベリー、ぶどう(皮が黒いものならレーズンでも)、桑の実、ひじきなど
【緑の濃いもの】
ほうれん草、小松菜、あしたば、えごまの葉、枝豆、パセリ、ヨモギなど

ビーツの煮物
赤くも黒くも緑でもないのに、血を補うものもあります。
主に魚介類で、あさり、イカ、イワシ、牡蠣、鮭、サバ、ブリ、マナガツオなどです。
薬膳では、体の構成要素のうち、血と津液は液体なので陰陽に分けると陰の性質を持つものになります。
なので、陰=海から獲れるものを食べると体の陰の成分が増え、そこから血も生まれるということです。
これらの食材を使えば、ほうれん草と牡蠣のグラタンや、ほうれん草の黒ごま和え、にんじん、枝豆を入れたひじきの煮物などの組み合わせで補血薬膳になります。
血を作る働きをする五臓の腎を補強する
直接、補血の食材を食べるだけでなく、同時に血を作る五臓の腎の補強をしておくと、腎が良く働いて血を作ることができます。
上に挙げた食材の中で腎を補強することができるのは、黒豆・黒ごま・あしたば・えごまの葉・枝豆・よもぎ・桑の実・ぶどう・赤貝・カツオ・ひじき・ブリ・鶏レバーです。
これ以外では、黒米・むかご・山芋・カリフラワー・ニラ・ブロッコリー・カシューナッツ・栗・エビ・ししゃも・帆立・うずらの玉子などがあります。
腎は冷えに弱いので、温かい状態で食べる煮物やスープなどがおすすめです。
冷やす性質のものは避けるか、食べるなら温める性質を持つ食材と組み合わせて冷やす性質を緩和させる食べ方をします。
これは、胃腸を冷やさないようにするためでもあり、胃腸が順調に動けば補血食材や腎を補強する補腎食材がしっかり消化され効率よく吸収されます。
すると、血も作られやすいということなのです。
献血の後、食べると即効性があるのは動物性のもの
色々ある補血食材のうち、即効性があるのは動物性のものになります。
それは、人間も動物なので親和性が高いからです。
牛の赤身のラズベリーソース添えや鶏レバーを使ったニラレバ炒めなどがこれに当たります。
献血によって減少した血液量は3~4時間で回復すると言われていますが、全血献血(すべての成分を献血する)場合、無くなった赤血球の回復が最も遅く3~4週間かかるそうです。
なので、即効性のある動物性の材料を使った食事をしながら、野菜や魚介類を合わせて行くと良いですね。

焼肉でも赤身の肉で
成分献血なら赤血球は戻される
全血献血は400mLと200mLの二種類ありますが、その他に成分献血もあります。
成分献血は回復に時間がかかる赤血球は戻し、血小板や血漿だけを献血する方法です。
献血当日は受付の後で問診や血圧測定、ヘモグロビン濃度測定などの事前検査を受けます。
どんなに献血する気満々でも、ここで基準値に達していない場合は献血はできません。
献血に要する時間は、全血献血で10分~15分程度、成分献血で40分~90分程度かかります。
一気に抜くわけではないので、基準値の血液を持っている健康な人は特に問題なく受けられますが、献血後は激しい運動をしたり男性が献血した後のトイレは着座で済ませることなどの注意事項を守りましょう。
献血した後だけでなく、献血すると決めたら食べ物に気をつける
献血をした後に食べるとよい食事は今まで書いたものですが、献血をすると決めたら日頃から補血と補腎の食事をしておくと献血後の回復が早いですね。
そして、誰かのためになる血液ですから少しでも良質な方が良いですし。
何より、善意で献血したのにその後がフラフラになって仕事にならないとか、疲れてしまう、集中できないということにならないためにも、日頃から補血と補腎、そして胃腸を元気な状態にしておくことを心がけておくと良いですね。
まとめ
献血の後に食べると良い食事を薬膳で考えるなら、体の構成要素の一つの血を補う補血食材と、血を作る五臓の腎の補強の補腎食材を食べます。
補血食材は色で言うと、赤いもの・黒いもの・緑の濃いものですがこの三色に当てはまらなくても補血が得意な食材もあります。
それは主に魚介類で、陰の性質の海から獲れるものと考えます。
補血食材と補腎食材を組み合わせた食事で献血で失った血液を早く回復するために、人間と親和性の高い動物性のものを摂り入れると即効性があります。
そして、これらの食事を効率よく吸収するためには冷えに弱い胃腸と腎の保護のために、温かい調理法で食べることと、胃腸を健康に保つことも一緒に考えてください。
また、献血の後だけでなく、献血前にもこれらの食事を日ごろから摂ることで献血後の回復も早くなります。
【関連記事】
【参考】






