
節分は、二十四節気の最後の日です。
節分の翌日は、立春で、暦の上では春の始まりの日に当たり二十四節気の始まりの節気です。
八十八夜、二百十日などは、立春を起点にしたもの。
節分の行事食である豆まきの大豆と恵方巻。この二つは食材の性質や効能的に組み合わせることに意味がある薬膳です。
恵方巻を食べる時は、豆まきの大豆もぜひ食べるようにしてください。
節分は言わば、大晦日です。
節を分けると書きますね。
節分には、豆をまいて季節の変わり目に起こりやすい災いや病気を鬼に見立てて追い払う習わしがあります。
一般的には「鬼は外、福は内」と声を出しながら福豆(煎り大豆)を撒いて、年齢の数だけ(もしくは1つ多く)豆を食べる厄除けを行う。また、玄関などに邪気除けの柊鰯などを飾る。これらは、地方や神社などによって異なってくる(後述)。
ウィキペディアより
そして、関西を中心とした風習の、その年の吉方位(恵方)を向き、巻き寿司を一本しゃべらずに完食する食べ方をするのが恵方巻。
恵方巻も節分の行事食として全国的に広まりました。
豆まきの大豆と恵方巻。この二つの薬膳的な意味を知っていますか?
恵方巻を食べる時は、豆まきの大豆もぜひ食べるようにしてください。
節分の豆の薬膳的効能
地面に埋めておくとそこから芽が出る穀物類は薬膳でも「気」を補う食材と考えられていますが、豆まきの福豆には神が宿ると言われます。
一年の最後に、それまでの悪いものを追い払ってもらい(「魔」を「滅する」で豆(まめ)を撒くとも言われます。)、福が呼び寄せられるようにするのが節分の豆まきの意味ですね。
殻付きの落花生を使う地域もあるようです。
所説ありますが、もともとは煎った大豆が使われていたようですので、ここでは大豆の薬膳的な効能を述べます。
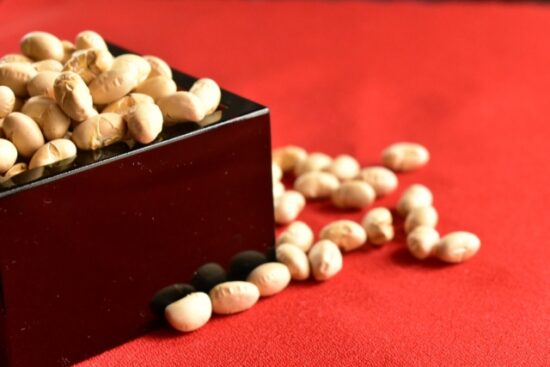
大豆は、体の構成要素である「気・血・津液」の「気」を補う効能があり、「気」とはスタミナやパワーのようなものに当たります。
大豆を「気」に変えるのは消化器系である五臓の脾。
大豆には脾を丈夫にさせて、「気」を効率よく作るという効能が言われているのです。
「脾」が健康的に機能していれば、水巡りもスムーズで、浮腫みや重だるさを感じにくい体でいられます。
「脾」が元気になる味があり、それは甘味です。
適度な甘味は「脾」を健康な状態に保つための味。
この甘味は砂糖の甘味ではなく、豆類や芋類、米やとうもろこし、かぼちゃなどに含まれる天然のやさしい甘味の事を言います。
味の点からも、薬膳では大豆が「脾」にとって良いと言われていることがわかります。

次に、恵方巻についてです。
節分の恵方巻の特徴
恵方巻は、江戸時代から明治時代に関西で生まれた節分の習慣だと言われています。
有力とされている説は大阪の商人や芸子が、無病息災と商売繁盛を祈願して節分に巻きずしを食べるようになったというものです。

恵方巻の具は7種類。
これは、七福神にあやかり、福を巻き込む意味が込められています。
巻き込む具材に決まりはありませんが、一般的には、うなぎ(穴子)の蒲焼、かんぴょうの煮物、干し椎茸の煮物、きゅうり、蒸したエビ、桜でんぶ、だて巻き(玉子焼き)の7種類。
うなぎ(穴子)、かんぴょうなどの長いものには「長寿」を願い、傘に形が似ている椎茸に「身を守る」、「九利」の当て字から「九つの利を得る」できゅうり、ひげが長く腰が曲がった様子から「長寿」の意味でエビ、鯛を中心とした白身魚で作る桜でんぶに「めでたい」、黄色を「金」に見立てて「金運」でだて巻き(玉子焼き)と縁起をかついだ意味が言われています。
薬膳で考えた時、思いのほか、砂糖が使われている料理なのが分かります。
甘味は「脾」のために良い味だとは言っても、煮物に砂糖を使う具材中心の恵方巻の場合、思っているより多い甘味を摂ることになってしまいます。
具だけではなく、巻き寿司には酢飯を使いますが、酢飯にも砂糖を使うのです。
ヘルシーだと思って日本のお寿司を食べるようになった海外の方が、こんなに砂糖を使うのかと驚かれると聞いたことがあります。
甘い味の恵方巻は、結果的に「脾」を弱らせる可能性があるのです。
大豆と恵方巻の組み合わせの意味
このように、恵方巻だけを食べると、人によっては翌日、普段よりむくみを感じたり、重だるさを感じる人がいるかもしれません。
大豆には、「脾」を丈夫にさせて要らない水分を排泄させる効能があります。
そのため、恵方巻と大豆を両方食べることは薬膳的には砂糖の影響で「脾」が弱るのを緩和させる「なかったことにする薬膳」になります。
大豆は年齢の数だけ食べることになっていますが、ここで注意が必要です。
大豆を食べる時の注意
煎った大豆は硬いので、よく噛んで食べることです。
いくら歳の数とは言っても、一度に何十個も食べると、お腹が張ってガスが溜まる人もいます。
お腹が張るのは「気」が溜まり、巡っていないからです。
一度にたくさん食べないことや、食べる時にはよく噛んで食べるようにしましょう。
節分に、なかったことにする薬膳をプラスする一品
恵方巻と大豆のなかったことにする薬膳にプラスして、すでに浮腫みやだるさを感じていたり、もともと胃腸が弱めな場合は、一品プラスしてはいかがでしょうか。
わかめやもずくを使ったお吸い物やみそ汁です。
巻き寿司は熱々で食べる料理ではないため、温かい料理を一品加えることで胃腸を温めることができます。

海藻類は、浮腫みやだるさの原因になる、体に溜まった要らない水分やその水分が粘度を持ち、出しにくくなったものを溶かして排泄させる軟堅作用があります。
お吸い物には、三つ葉などの香りのよい香味野菜や柚子皮を添えて「気」を巡らせます。
「気」を巡らせることによりお腹の張りも解消されやすく、水巡りも促されます。
まとめ
節分の行事食の代表、恵方巻と大豆の組み合わせには、このように薬膳的な効能があります。
昔からある行事食には、無病息災や健康祈願などの意味だけでなく、意外と知られていない食材の性質や効能を使った薬膳になっている場合があります。
煮物が多い和食には、海藻や豆類で、砂糖の影響を緩和させる食材の組み合わせ。知らず知らずにやっているものです。
恵方巻を食べるなら大豆も食べることで、砂糖の影響を緩和します。
そこに海藻を使い香りを加えるとさらに体への影響が緩和される薬膳になります。
節分の行事食を楽しんでくださいね。
【関連記事】






