
日本には梅雨があり、湿度が高いため日本人は湿気の影響を受けた体質だと言われます。
梅雨だけでなく、雨が降り続く時期や台風時期などの湿気が高い時にも使えるので、湿度が高い時におすすめのお茶を薬膳の視点からご紹介します。
そして、どんなにおすすめのお茶を飲んでも、これをやっていると不調になりやすい原因も解説します。
目次
湿度が高い時におすすめのお茶はこれ!
薬膳の基になる中医学では、どんな人も一人一人体質が違い個人差があることを大切にしています。
そのため、同じ悩みであっても、ある人には向いていても別の人には向いていないと言うものもあります。
食材にはどんなものでも、それを体に入れると体が温められる温熱性のもの、体にこもった熱を冷ますことができる寒涼性のもの、その間のどちらでもない平性と大きく分けた三つの性質があります。
冷え性の人が、体を冷やす性質のものを摂れば冷え性はさらに酷くなりますし、体に熱がこもっている人が温めるものを摂ればもっと暑くなってしまいます。
そのため、どちらでもないものに分類される「平性」のお茶を「比較的誰にでも合うお茶」とします。
ここでは比較的誰にでも合う、湿気が高い時におすすめのお茶を2種類、少し気をつけて使って欲しいお茶を3種類ご紹介します。
湿度が高い時に比較的誰にでも合うお茶2選
1.とうもろこしのひげ入りコーン茶
とうもろこしは、消化器系に当たる五臓の「脾」を丈夫にする効能があります。
水分代謝を促進する働きもありますが、特に実の周りを覆っているひげにその効能が高いのです。
薄緑の柔らかい部分を天日干ししたものは「玉米髭(ぎょくべいじゅ)」という生薬(※)です。

とうもろこしご飯にひげを刻んで一緒に炊き込むのは、薬膳でお勧めするとうもろこしご飯の作り方ですが、お茶でも「コーン茶」にひげが入ったものが湿度が高い時には特におすすめのお茶となります。
(※)生薬とは、植物の根・茎・葉・実・樹皮、鉱物、貝、動物、昆虫などを乾燥させたものを中心とした漢方薬の材料となるもの。
2.黒豆茶
黒豆は黒大豆の事です。
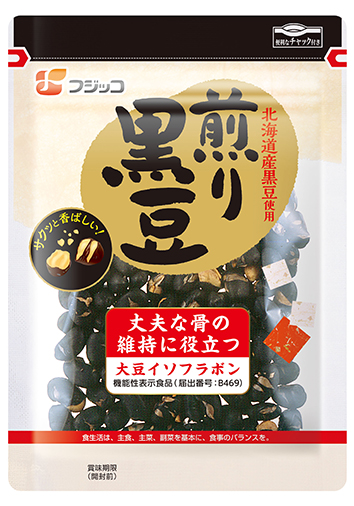
薬膳では、黒豆や黒ごま、黒きくらげなどの黒い食材は、老化と関わる五臓の「腎」の働きを高める食材と言われています。
黒豆は、女性に不足しがちな体の構成要素「気・血・津液」の「血(けつ)」を補い、特に湿度が高くて汗が出る時期に、汗と一緒に流れ出てしまう「気」も補うことができる食材です。
大豆の持つ「脾」の機能を高めるため、水分代謝を促し湿気の多い時におすすめのお茶の一つです。
特に、40代以降の女性は家庭でも社会でも責任ある立場となり自分の事を後回しにしてしまう人が少なくありません。
この世代は食事でも自分は、食べた気になり家族の事を優先させたり、仕事の多忙さから食事が不規則になる人もいます。
そこから更年期の不調が酷くなる人もいるので、エイジングケアを考える人に湿度が高い時におすすめのお茶は黒豆茶です。
更年期以降は、体の潤い成分も減少しがち。その結果、お肌の乾燥や目や口などの粘膜の乾燥も見られます。
黒豆を煎ったものをお茶として飲んだり、黒豆を煮た煮汁はのどの炎症を解消します。
カラ咳が気になる時にもおすすめです。
この2種類は、体を温めも冷やしもしない平性なので、冷え性の人でも体に熱をこもらせている人にもマイナスの影響にはなりにくいです。
主に、消化器系の働きに当たる「脾」の機能を下げないようにして水分代謝を促す効能があるため、湿気が高い時の基本のお茶と言えるでしょう。
次に、少し気をつけて選んで欲しいお茶のご紹介です。
湿度が高い時に気をつけて選びたいお茶3選
少し気をつけて選んで欲しい訳は、基本の効能にプラスαの特性があるからです。
特にもともとの体質や、妊娠などによって普段の体調より敏感になっている時に気をつけて選ぶ必要があるものです。
1.はと麦茶
はと麦は体にこもった熱を冷ます涼性の食材で、消化器系の働きを高め水分代謝を促します。
はと麦は「薏苡仁(よくいにん)」という生薬名があり、漢方薬にも使われています。
浮腫みの解消、水いぼの解消や美肌効果が謳われていて、ハトムギ化粧水などで知っている人も多いのではないでしょうか。

「麦」と付いていても麦の仲間ではなく、イネ科の植物の一種です。
薬膳食材としては、皮を取り除いたものを茹でたりご飯に炊き込んだりして使います。
薬膳茶にする時は、皮ごと煎ってあり、香ばしい味は麦茶に似ているため飲みやすい薬膳茶です。
湿度が高く気温も高い時は、冷やして体に溜まった要らない水分を代謝することを促しますが少し注意が必要です。
体を冷やす性質があるため、胃腸が冷えやすい人は飲み過ぎに気をつけてください。
焙煎されているため、冷やす性質は緩和されていますが、もともとの冷えの状態は人それぞれなので飲んでみて合うか合わないかの判断をしてください。
そして、もう二つ忘れて欲しくないことがあります。
一つ目ははと麦は、妊婦さんには禁忌とされている食材だと言うこと。
はと麦には、胃腸の働きを高めて老廃物を排泄させる効能があるため、薬膳では下に降ろす特性があると考えます。
そのため、念のためにはと麦茶は妊娠の可能性がある場合には気をつけてください。
二つ目は、はと麦がイネ科の植物と言うこと。イネ科アレルギーの場合にも避けた方が無難です。
2.小豆茶
ペットボトルに入った小豆茶を見たことがあるかもしれません。
赤色が邪気を払うとされ、毎月1日と15日に小豆粥を食べる風習もあります。

皮の赤い色に含まれるサポニンと豆に豊富な食物繊維、カリウムが体に溜まった要らない水分の排泄や通便を促す食材です。
平性食材なのですが、体にこもった熱を冷ます特性があり、利尿作用が強いため更年期世代で火照りやホットフラッシュ、手足の熱感、夕方から微熱のような感覚のある場合は、注意が必要です。
これらの症状は中医学で「陰虚」と言われるもので、体の潤い成分の不足から来ると考えられています。
小豆茶により、水分代謝をし過ぎてさらに潤い不足になってしまう可能性があるためです。
常飲は避けて、湿度が高い日が続き重だるさやむくみが続く時に、体の状態を見て飲むようにすると良いお茶です。
小豆の摂り方についてはこちらのYouTubeでも解説しています。
3.ハブ茶
ハブ茶は、生薬名で「決明子(けつめいし)」と言われるエビスグサの種を乾燥させたものをお茶として飲みます。
体にこもった熱を冷ます微寒性で、目の充血やかすみ目、湿度が高い日に起こる頭痛、回転性のめまいに良いとされています。
体に溜まった要らない水分を尿として出すより便として出す効能が高いため、水分代謝が悪い場合はお腹が緩くなるため下痢しやすいタイプには注意が必要です。
おすすめのお茶は、湿度が高い時の体のバランスを調整する
これまでご紹介して来たお茶には、共通の効能があります。
それは、湿気によりスムーズでなくなる水分代謝を促すこと。
湿度の高い雨の日に洗濯物がなかなか乾かないように、人間の体にも湿気が影響します。
普段なら呼吸や汗、尿で排泄される要らない水分が体から出にくくなるのです。
スムーズな排泄を促すために、食材の特性を使うのが薬膳の考え方です。
多すぎるものは出す。そのためにはとうもろこしやそのひげ、黒豆、はと麦、小豆、決明子などの効能が使えるのです。
ですが、ただ出せばいいだけではありません。
湿度により弱る体のシステムが要らない水分が溜まりやすい体にしてしまうからです。
おすすめのお茶は湿度で消化器系のシステムが弱らないようにする
湿度により弱る体のシステムは消化器系です。
中医学では「脾」と「胃」です。
「脾」と「胃」は冷えと湿気に弱いため、ジメジメする日が続いたり、雨に濡れてもすぐに拭いたり着替えたりしないでいると冷えて弱ってしまうのです。
消化器系が弱ると水分代謝が悪くなり、本来排泄される水分が排泄されず残るため、むくみや重だるさなどの原因となります。
おすすめのお茶のうち、とうもろこしのひげ入りコーン茶や黒豆茶、はと麦茶は水分代謝の促進だけでなく、消化器系を弱らせないようにする効能も併せ持っています。
ただ、湿気と冷えに弱い「脾」と「胃」を弱らせないために、どんなお茶でも次の事に気をつけて飲みましょう。
■ たくさん飲み過ぎない。
一度に大量に飲むのではなく、ひとくちずつ何度にも分けて時間を空けて飲みましょう。
運動や作業などで大量に汗をかいた時は、飲む間隔を短めに。
■ 冷たくして飲まない。
冷蔵庫で冷やしたものや氷を入れて冷やしたものは、消化を担当する「脾」と「胃」の働きを弱めます。
水分代謝が弱まるだけでなく消化力も弱まるため、特に夏の湿気対策として冷たいお茶は避けた方が無難です。
消化力が弱まると、下痢や未消化でお腹が空かない、便秘で食欲不振などに繋がり夏バテの原因になるからです。
そして、もう一つ。
同じものを長期間大量に摂り続けないことです。
どんなに良いものでも、ほどほどに。体調や天候などに合わせて変えることが大切です。
湿度が高い時におすすめのお茶まとめ
湿度が高い時におすすめのお茶を、比較的誰にでも合うお茶と、気をつけて選びたいお茶に分けて紹介しました。
誰にでも合いやすいお茶は、体を温めも冷やしもしない平性なので、冷え性の人にも熱をこもらせている人にも影響がなく、湿度対策になるお茶です。
これらのお茶の効能は、次の二つ。
●要らない水分を排泄させる
●湿度で弱りやすい消化器系を弱らせず丈夫にする
気をつけて選んで欲しいお茶は、体質や体の状態によっては飲まないか飲む量に気をつけるものです。
特に、はと麦は妊娠中は気をつけてください。
更年期で火照りなどがある時は、小豆茶も短期間にしておきましょう。
そして、湿気と冷えに弱い消化器系が弱れば、要らない水分を排泄させても溜め込みやすい体質になってしまいます。
そのため消化器系を弱らせないように、一度に大量に飲まないことと冷たくして飲まないこと。
また、同じものを長期間飲み続けないことも心掛けてください。
【関連記事】






