豆乳鍋や豆乳を使ったスープを作る時に、うまく行かないことはないですか?
失敗になるのは、豆乳が分離してボロボロと塊ができてしまう状態です。
豆乳に含まれているたんぱく質が熱と塩分によって固まるのです。
そのまま静かにしていれば湯葉ができますが、かき混ぜたりお鍋は食べている間に具を動かすことになるためボロボロ状態になるという訳です。
豆乳鍋を分離させない方法は、塩と油にポイントがあります。
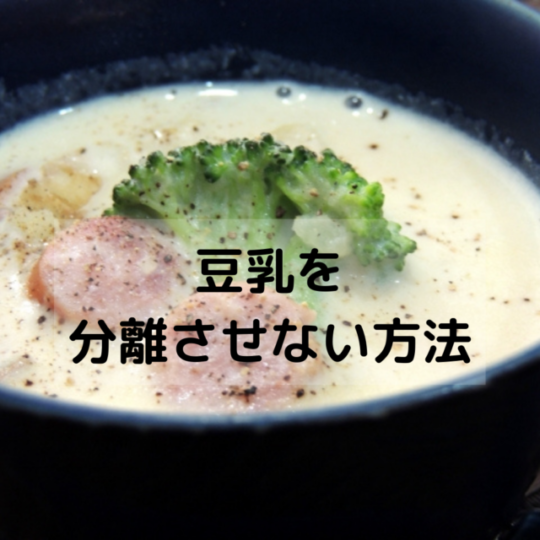
目次
豆乳の種類でも分離が違う
豆乳には、無調整豆乳と調整豆乳があり無調整豆乳は、にがりを加えると豆腐ができる状態の物です。
日本農林規格(JAS)の定義によると、
調整豆乳は大豆の絞り汁に大豆油や砂糖、塩などを加えたもので大豆固形分が6%以上の物となります。これをたんぱく質量に換算すると3.0%になります。
簡単に言うと大豆の絞り汁そのもので大豆固形分が8%以上のもの。たんぱく質量が3.8%以上の物が無調整豆乳です。
たんぱく質が多く味付けがない、豆腐ができる前の状態のものが無調整豆乳ということになります。
お鍋やスープに使うのであれば無調整豆乳を選びます。
調整豆乳を使えば、分離しにくくなります。それは、大豆油を添加されていることとたんぱく質の量が無調整豆乳より少ないからです。
その分たんぱく質は少なく場合によっては味がお鍋やスープに合わないこともあるでしょう。
なので、アラフィフ世代が食事として使うなら無調整豆乳を選びましょう。
無調整豆乳を使って分離させないために豆乳鍋に油脂を含んだものを入れる
調整豆乳には大豆油が入っていることも、分離しにくい理由でした。
それなら無調整豆乳を使っても油脂を使えば分離しにくいと思いませんか?
薬膳では、豆乳は更年期以降の女性の潤いをアップさせる食材の一つです。
それに加えて同じく潤いアップの白ごまを使います。
簡単にお鍋やスープにするためには、白ごまペーストを使うのがおすすめです。
野菜などの具がしっかり煮えたら、一旦火を止め静かに豆乳を注ぎます。この時、かき混ぜないことがポイント。
豆乳を入れたら白ごまペーストを大さじ5杯程度加えて静かに混ぜます。
チューブタイプなら直径10センチを2周くらいです。

これでほぼ分離しなくなります。
豆乳はにがりで豆腐になるということから塩分で固まらせないために
豆乳から家庭で豆腐を作るにはにがりを入れて豆乳を温めます。
にがりを使うということは、天然の塩でも豆乳は固まるということになります。
にがりにはカリウムやカルシウムが豊富に含まれ、天然塩にもにがり同様にミネラル分が多いからです。
そこで、塩味をつける時に天然塩ではなく白味噌を使います。
白味噌は塩分が少ない発酵食品で薬膳的には潤わせる白い食材の一つと考えます。
白味噌を加えるとコクが出てまろやかな風味が感じられるようになります。
潤わせる食材×3で更に潤いアップの鍋やスープになる
豆乳を分離させないための、白ごまペーストと白味噌ですが、薬膳の視点からは3つとも潤わせ食材なのです。
そのため、この3つを使って潤わせる薬膳ができます。
中華でも、和風の鍋でも、クリームシチューやクリームシチューのリメイクでクリームパスタにすることも。
ラーメンのスープにする時はごまペースト多めで、豆板醤やラー油も加えるとピリ辛担々麺風になります。
ごま油を少し入れると更に本格的に。
クリームシチューにするなら、えのきだけのみじん切り、山芋(長芋)、下ろしたレンコン、里芋などを入れるとルーがなくてもとろみがつきます。
イタリアンにするなら、オリーブオイルで炒めたにんにくのみじん切りか、にんにく風味をつけたオリーブオイルを加えます。
どれも濃厚で豊かな風味の薬膳になります。
まとめ
豆乳を分離させないための方法は、まず、豆乳を入れる時に煮立たせず静かに入れかき混ぜないことです。
豆乳のたんぱく質を固めるのは塩気なので、塩分を抑えます。
次に、加える油でも固まりにくくなるため、豆乳と同じく潤わせる効果のある白ごまペーストを使い、塩分は白味噌で補います。
三つがよく溶けたら塩で塩分を調節します。
中華風、洋風にするにはごまペーストの量や後からごま油やにんにくなどを加えて調味してください。
豆乳を分離させずに潤いアップの薬膳ができるコツをお伝えしました。
【関連記事】






