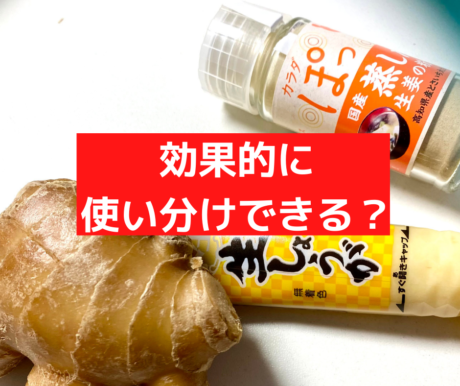
数年前にショウガブームがありました。
おろしショウガのマイチューブを持ち歩き、外食してもお茶を飲んでもチューブのおろしショウガを加えて食べたり飲んだりする人がいました。
薬膳では、ショウガは生の状態で使うのか、蒸して乾燥させたものを使うのかでは効能が違うことから、目的に合わせた生姜の効果的な摂り方をお伝えします。
目次
生姜で効果的に中まで温めたいのか、表面の寒気を飛ばしたいのかで摂り方を変える
薬膳では生のショウガを生姜(しょうきょう)と呼び、蒸して乾燥させたショウガを乾姜(かんきょう)と呼んで区別します。
※ここでは以降、漢字で生姜と書いた場合はしょうきょうを表し、ショウガ全般と分けて記載します。
生姜も乾姜も性質は温める性質ですが、熱を加えた乾姜は生姜が温性なのに対し熱性になりさらに強く熱を加える性質になります。
両者を効果的に使い分けるには、その効能の違いを知ることが必要です。
具体的には、まず体の中まで温めたいのか表面にある寒気を飛ばしたいのかで考えてどちらを選ぶか決めるとよいでしょう。
生姜は風邪のひき始めに使うのが効果的
生のショウガである生姜はどんな効能を持つのか?
生姜は表面の寒気を飛ばす、発散させる効能を持つのが特徴です。

風邪をひいたかもしれない!という背中がゾクゾクする時に、帰宅したらすぐに葛湯を作り最後におろしショウガを加えて飲むと一気に熱くなり汗をかきます。
これで体の表面にあり、中まで入っていない風邪をすばやく引きはがす、汗と一緒に発散させるという考え方です。
その他、皮には水巡りを改善する効能があるとされ皮はやや体を冷やします。
なので、真夏のそうめんの薬味として使う場合、冷房の効いた室内で食べるなら皮を剥いてからおろしショウガにして体表の寒気を飛ばし、キャンプや庭で流しそうめんにするなら
皮ごとおろしショウガにすれば皮を剥いてからおろすよりカーっと熱くなるのが少し緩和されます。
生姜の皮つき・皮なしでもその時の体にこもった熱の状態によって使い分けができます。
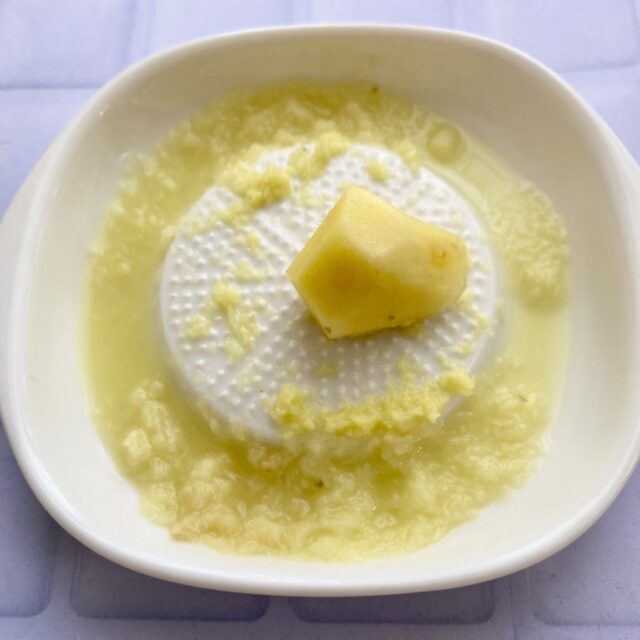
生姜は一気に温め、汗と一緒に表面の寒気を飛ばしその後スーッと体が冷えるため風邪のひき始めに使い、おろしショウガを入れた葛湯を飲んだら布団をかけて直ぐに寝ることが
ひき始めの風邪を早く治すコツと言えます。
乾姜はお腹の中からしっかり温めたい時使うのが効果的
ショウガを蒸して乾燥させた乾姜は、生姜より強く温める性質を持ち、お腹の内側から温める働きがあります。
お腹が冷えて痛む時、冷えて吐き気や下痢の時、生姜よりも効果を発揮します。
その代わり、生姜のように一気に熱くして汗をかき表面の寒気を飛ばす、発散させる効能はやわらぎお腹の中からじわじわとしっかり温める効果があります。
胃腸が冷えて不調の時は、乾姜を使う方が効果的です。
昔からの食の知恵で使われる生姜の効果的な使い方
その他、ショウガには解毒作用があるとされます。
これを利用したものが刺身の薬味に使う方法です。
鰹やアジなどの青背の魚は傷みやすいので、青魚の薬味にはよくおろしショウガが使われます。
これはショウガの持つジンゲロールという成分の働きによります。
ジンゲロールは殺菌作用や、魚の臭み取り、食中毒予防になります。
ジメジメとした梅雨から日本の夏は、湿気により胃腸が弱りやすい季節です。
日本人のお腹を温めて浮腫み改善と食中毒予防にもなるショウガは昔からよく使われて来た食材と言えますね。
乾姜がなかった時は生のショウガを調理して使うと乾姜の効果が期待できる
生姜と乾姜の違いと使い分けがわかったところで、わざわざ生のショウガを蒸して乾燥させるのは少し手間です。
市販の乾姜を買うのも一つですし、蒸し生姜パウダーも販売されています。

でも、スーパーで売られているショウガでも乾姜と同じような効能を得ることができます。
それは、普段の料理の時にショウガを調理すればよいのです。
アサリの酒蒸しの時にショウガを入れる。
同様にアサリご飯にショウガの千切りを入れる。
これはアサリの冷やす性質を緩和させる「なかったことにする薬膳」の手法の一つです。
※「なかったことにする薬膳」は必要な食材の効能は利用したいが、自分に不要な性質や効能を他の食材との組み合わせで緩和させ「なかったことにする」メソッドです。
中華料理の最初に、ねぎ、ショウガ、にんにくを炒めます。
肉の臭みを消すためですが、これでも生のショウガを炒めることで乾姜の効能を得ることができると言えます。
みそ汁やスープに使う時も目的に合わせてショウガを効果的に使う
今までお伝えしてきたように、生姜が必要なのか乾姜が必要なのかによって、味噌汁やスープに使うショウガも生なのか熱を加えるのかを変えると良いですね。
風邪のひき始め、罹ったかな?の時は出来上がったスープやみそ汁におろしショウガや生の針ショウガをトッピング。
寒い場所に長時間居て体の芯から冷えてしまった、冷たいものの食べ過ぎ飲み過ぎでお腹が冷えて調子が悪い時は、スープやみそ汁の具と一緒にショウガを煮込んでしまう。
この使い方の違いでショウガをその時必要な目的に合わせて効果的に使うことができます。
チューブのおろしショウガは生姜と同じ効果があるのか?
おろしショウガにするのが面倒な時、便利なのはチューブのおろしショウガですね?
でも、原材料を見たことがありますか?
おろしショウガだけが欲しいのに、実にいろいろなものが入っているのに気づきます。
できればその都度、生のショウガをおろして使って欲しいですが、どうしても面倒な時は無添加のおろしショウガを使ってください。
楽天ROOMでもご紹介しています。
または、おろしショウガを小分けして冷凍しておくと便利です。


ショウガの食べ過ぎに注意が必要な人
ショウガが良いからと言って、ブームの時のように常に摂り続けるのは考えものです。
特に、体に必要な潤い成分「気血津液」の津液不足の人、血不足の人が生姜を食べ過ぎるとさらに潤い水分不足になり体に不要な熱がこもってしまいます。
それにより、更年期世代以降はホットフラッシュや頭部の火照りなどに繋がる可能性があるので、必要な時にほどほどに摂るようにしてください。
同様に、皮膚にできものができて熱感がある時も気をつけてください。
まとめ
薬膳の視点から見たショウガの効果的な摂り方は、その時の体調に合わせて生で摂るか熱を加えたものを摂るかを決めることが大切です。
表面の寒気を飛ばしたい時、風邪のひき始めの時は生の生姜をおろしショウガなどで。
お腹の中からじわじわとしっかり温めたい時は蒸して乾燥させた乾姜を使います。
乾姜が手に入りにくい時は、スーパーで購入したショウガを調理して使うと乾姜と同様な効果が得られます。
チューブのおろしショウガには添加物も多く、同量のおろしショウガよりショウガ自体の量が少ないのでできるだけその都度おろして使うのがおすすめです。
それでも面倒な時は、無添加のおろしショウガチューブを使うようにしてみてください。
冬以外の季節でも効果的にショウガを使って健康管理の一環にして行きましょう。
【関連動画】
チューブのショウガの知られていない効果!正しく生姜を食べる!!
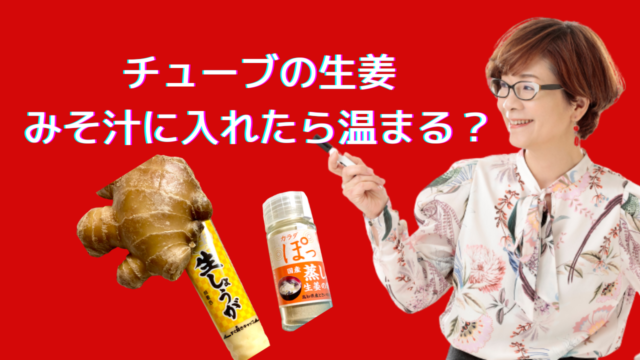
【関連記事】
【参考サイト】






