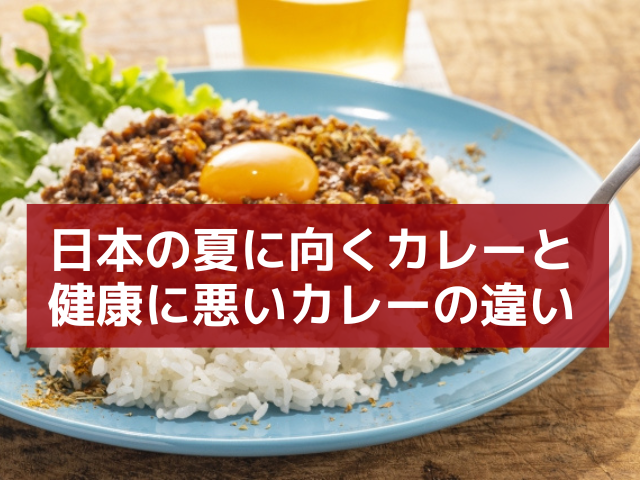
スパイスが食欲を増すため、夏になるとカレーを食べる人も多くなります。
カレーは薬膳だから、スタミナが付くからなどと良いイメージが先行していますが、体に良いと思って食べているカレーでもかえって健康に悪い場合もあります。
ここでは、日本の夏に向くカレーと向かないカレーを中医学と薬膳の視点から解説します。
目次
健康面から考えて日本の夏に向かないカレー
日本の夏は暑さだけでなく蒸し暑さが特徴ですね。
暑いと汗で体温調節をしますが、水分だけで失った体液を補充しようとしていると、ただ体の中を流しているだけで細胞をしっかり潤せていない場合があります。
汗をかくことで、体温調節ができ一旦涼しさを感じますが、カレーのスパイスは体を強く温めます。
そのため、体温が上昇するので汗をかいて冷却するのです。
ところが、更年期以降の女性や男性高齢者は体の潤い不足の陰虚の状態になっています。
その状態で辛いカレーを食べると汗で潤いが失われ、更に陰虚が進んでしまいます。
日本の夏に向かないカレーの一つ目は辛すぎるカレーです。
辛すぎるカレーが健康に悪い理由
暑がりで、常に氷水や冷たい飲み物を飲んでいる人は、必要な水分を体に溜めておくことが苦手なタイプかもしれません。
このタイプは、日頃からトイレが近くよく汗をかきます。
その状態で辛いカレーを食べて大量の水を飲む行為は、上がった体温を下げようと何杯も水を欲する割になかなか冷やすことができません。
そのため大量の水分を摂ることになるのです。
汗は体温調節だけでなく老廃物を出すので、たくさんかいた方が良いと思われがちですが、ぐっしょり濡れるほど汗をかいた後は疲れを感じることはありませんか?
これは、汗と一緒に体の構成要素の「気」が出て行ってしまうからです。
「気」は臓器を機能させたり、血巡りや水巡りなどに関係する大切な要素なので、気が失われた気虚だとだるく感じたり、気力が無くなり、何より消化器系の働きが落ちて夏バテになってしまう可能性があります。
スタミナをつけようとカレーを食べたのにかえってこれでは逆効果なのです。
また、水分を摂ってもトイレにあまり行かない人もいます。
汗はかきますが飲んでいる割にトイレに行かないと過剰な水分は体の中に溜めることになりますね?
つまり、むくみや水太りになってしまうのです。
このタイプが辛すぎるカレーを食べて大量に水を飲むと、更にむくみ重だるくなってしまいます。
余りに辛すぎるカレーはこのように健康的ではないのです。
次に一般的に家庭で作るカレーに使うルーを見てみましょう。
日本の夏にカレーで胃もたれを起こす原因
市販のカレールーの多くは油脂がたくさん使われています。
原材料表記を見ると、割合の多いものから書かれているのでカレーより油脂の方が多いのが分かると思います。
この油脂の多さが、日本の夏には向かないのです。
なぜなら、日本の夏は湿度の高さが人の体にも影響し、消化器系に当たる五臓の「脾」を弱らせる季節だからです。
「脾」が弱っている所に、更に追い打ちをかけるのが油脂。
「脾」は湿気だけでなく、脂っこいものやこってりしたもの、砂糖を使った甘い味付けの物で弱りやすいのです。
油脂はほとんどが牛脂や豚脂です。
牛脂と言えばすき焼きで肉を焼く白い塊。
熱が加われば液体になりますが、冷えれば固形です。
冷たい飲み物や食べ物を摂る機会の多い夏は、サラサラの状態から冷やされて元の固形状態に近くなるイメージです。
冷たい水を飲みながら、牛脂や豚脂の入ったルーで作るカレーが胃もたれする原因はこれです。
日本の夏に向かないカレーの二つ目は油脂を多く使ったルーで作るカレーということです。
カレーが好きな人の食べ方を見てみると「カレーは飲み物」なんて言う言葉が浮かびます。
カレーをご飯にかけて食べるカレーライスだと、あまり噛まずに飲むように食べてしまうからです。
あまり噛まずに食べるとどんな点でカレーが健康に悪い原因になるのでしょうか。
夏にカレーをあまり噛まないのは特に健康に悪い
どんな食事にせよ、よく噛むことは大切です。
あまり噛まずに食べることの弊害は、満腹中枢が働いて満腹感を感じる前にたくさん食べてしまうこと。
もうひとつは、噛むことは食物を細かく砕くだけでなく、唾液を混ぜることで消化酵素を混ぜた状態で胃に送れる状態にします。
そして、噛むことで胃にも刺激が加わり、胃の消化酵素が分泌されるので入って来た食物をしっかり消化するスタンバイができるのです。
あまり噛まずに飲んでしまうとこれらができず、胃に負担がかかるのです。
胃で消化するためにエネルギーを使うことは「気」を消費すると言うことなので、疲労や夏バテ予防には「カレーは飲み物」なんて避けたいのです。
この点から、カレーをしっかり噛める状態にするか、もしくは食べ慣れたカレーでも意識してよく噛むことが大切です。
日本の夏に向かないカレーの三つ目は噛まなくても食べられてしまうカレーです。

このようなカレーは日本の夏の気候に合わず、健康に悪いカレーと言えるでしょう。
では次に、これまでの事を踏まえて健康的なカレーについて書いていきます。
日本の夏の特徴を考えた健康的なカレー
日本の夏が暑さと湿度と言う特徴を持つため、次のことに気をつけたカレーなら健康的なカレーと言えます。
1.辛すぎないカレー
辛いことが悪いと言うより強く体を温めるため、体温が上がり必要以上に汗をかいてしまいます。
食べながら大量の水を飲めば胃液が薄まり、消化力が落ちることになります。
また、消化器系のシステムは湿気だけでなく冷えにも弱い特徴があります。
大量の冷たい水はまさに消化器系を弱らせる条件が揃っていると言うこと。
辛すぎなければ、水を飲んでも飲みすぎるほどは飲まないで済みます。
特に潤い不足の更年期以上の女性と高齢男性は激辛カレーは避けるべきでしょう。
2.ルーに牛脂や豚脂が使われていないカレー
スパイスカレーと言って自分でスパイスを調合してカレーを作れば牛脂や豚脂が入ったルーを使わなくても作れます。
ですが、市販のカレールーでもとろみつけやコクを他の材料で補っているものもあります。
ルーを購入する時に、裏の原材料を見て買うようにするだけで胃もたれの原因となりやすい油脂を避けることができます。
忙しい時にルーがあるのは便利ですよね。
市販の物でも小麦と動物性油脂を使っていないものがあるので、ネットでも検索してみることをおすすめします。
3.スープカレー・ドライカレーにする
トロリとしたルーがかけられたカレーはどうしてもあまり噛まずに食べてしまう!と言う方は、野菜や肉がゴロゴロ入ったスープカレーにしてはどうでしょう。
具が大きいのでしっかり噛まなけばなりません。噛めば満腹中枢が働くので食べ過ぎを防げます。
または、ドライカレーやひき肉を使ったキーマカレーの水分をなるべく少なく作ります。
水分が少ないので飲むようには食べられず、しっかり噛むことになりますね。

このように日本の夏の特徴から予測できる不調の原因になることを排除すれば、カレー自体はスパイスの効能で健康的に食べられるものです。
特に、スパイスの香りは「気」を巡らせるため食欲が増し、夏バテ予防の食事になります。
でも、やはり市販のカレールーのカレーがが食べたい時もあるでしょう。
最後に、市販のカレールーを使ったカレーでも使う食材に工夫をすれば、健康に悪いこともプラマイゼロになる方法をご紹介します。
健康に悪いかも?のカレーをプラマイゼロにする食べ方
激辛はプラマイゼロにすることはできないので、辛さは甘口から中辛にしてください。
カレーをかけるご飯を、とうもろこしのひげ入りとうもろこしご飯、昆布を入れて炊いたご飯、はと麦入りご飯、豆ごはんなどにします。

一緒に炊き込む食材は、消化器系の「脾」が弱ることで体に溜まりやすい要らない水分を排泄させる効能があるものです。
とうもろこしのひげは利尿効果が高く、実には「脾」の働きを高める作用があります。
昆布には脂で粘度を増す不要な水分をサラサラにして尿として排泄させる効能があります。
「脾」の働きを直接高める効能は無いので、カレーに入れる具で補います。
この場合は具に、かぼちゃや豆類などを加えると脾の働きを高めます。
はと麦も、不要な水分を排泄させ「脾」の機能を高めます。
次に、もしサラダを添えるなら、サラダにはクレソンやチシャ(サンチュ)、わかめ、緑豆もやしを入れます。

クレソンやチシャ(サンチュ)は牛脂や豚脂でドロドロになりやすい血(けつ)をサラサラにさせる効能があるからです。
クレソンが食べられるシーンはステーキの付け合わせ。チシャ(サンチュ)は焼肉ではないでしょうか?
これはそれぞれステーキの脂、カルビなどの焼肉の脂でドロドロになる血(けつ)をサラサラにする薬膳なのです。
わかめは昆布同様、「脾」の弱りから要らない水分が溜まりやすくなるため、排泄させる目的です。
緑豆もやしは、緑豆の体にこもった熱を冷まし要らない水分を排泄させます。

まとめ
カレーは薬膳だから、体に良いと思って食べていると、予想外に健康に悪い場合があることを中医学と薬膳の視点から解説しました。
湿気が多く暑い日本の夏に起こりやすい不調の予防ができてこそ、本来薬膳と言える料理です。
消化器系に当たる「脾」が弱れば、どんなに栄養のあるものを食べても、それが吸収されず栄養として取り入れられないばかりか、消化に「気」というパワーを使っているので、マイナスになってしまいます。
そのため、「脾」の負担にならないようにすることは大切ですが、同時に湿気で溜まりやすい不要な水分を排泄させる食事も意識しましょう。






