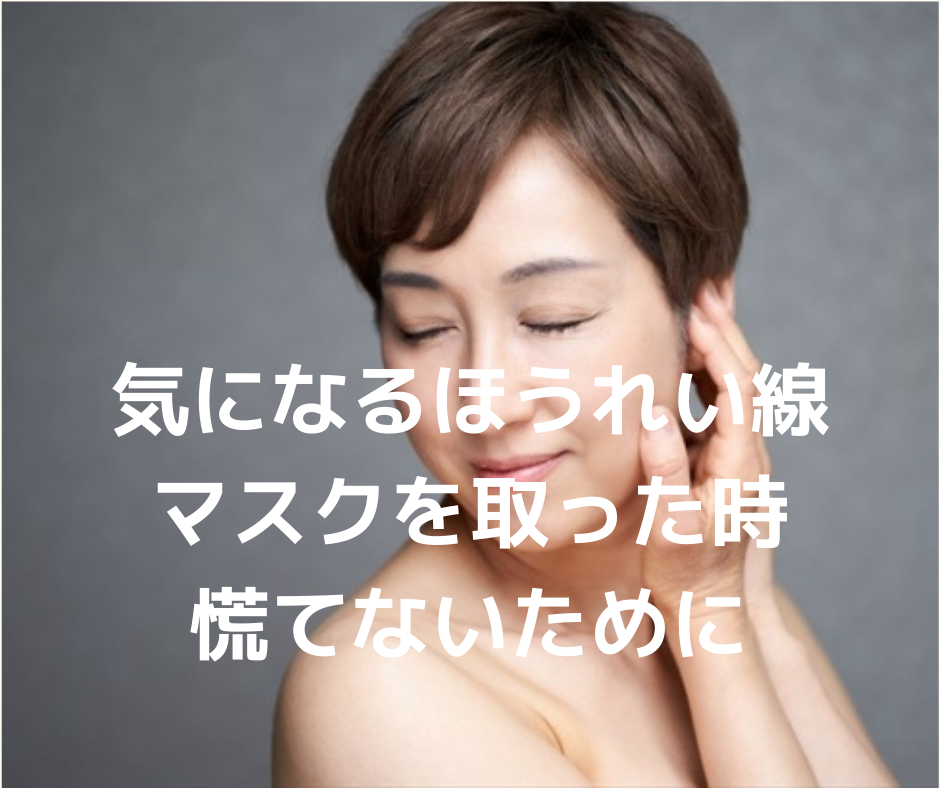
マスクをしているからとご自身のお顔に無頓着になっていませんか?
マスクを取った時に、頬が弛んでいたりほうれい線がくっきり、シワも増えていたということがあり得るかもしれません。
たるみや下がりが食生活と関係するの?と驚かれるかもしれませんが、これは薬膳の基になる中医学では有名なことなのです。
ここでは、中医学と薬膳の視点からほうれい線対策とおすすめの食べ物について解説します。
目次
消化器系に当たる「脾」が弱ると下に下がる
消化器系に当たる五臓の「脾」が弱ると、栄養が吸収されにくくなるため、筋肉がつきにくくなり、もち肌、ぷよぷよ系になって行きます。
アラフィフ世代は、若い時の様な十分なヒアルロン酸やコラーゲンも無くなってパーンと張った皮膚ではなくなってくるところに、消化器系を弱らせるとどうなるか?
消化器系は栄養の吸収と分配排泄をするだけでなく、水はけにも関わっているため、水を溜めやすくなってしまいます。
沢山の水分(脂肪も含む)は重いので下がります。
筋肉が少ないため、上に支えていられないのです。
そのため、頬の肉が下がりほうれい線がくっきりする。
目の下がたるむ、顎と首の境目があいまいになる・・・となってしまうんですね。
顔の上をコロコロする美顔器を使っていても、顔の筋肉を鍛える顔ヨガなどをやっていても、脾を弱らせていたら追いつかないのです。
せっかくその時は上がってもです。
特に、夏の時期は暑いために冷たいものを食べたり飲んだりする機会が増えますよね?
これが「脾」を弱らせて、マスクに隠れている頬、ほうれい線、顎のラインを緩ませ下がらせている原因という訳です。
ほうれい線が目立つ人の特徴
ほうれい線が目立つ人の特徴は、冷たいものをよく食べたり飲んだりしていることです。
お腹を冷やすと、熱は外に出て来るという法則が中医学では言われていて、表面温度が熱くて自分では暑がりだと思い込み冷たいものが手放せないのですよね。
お腹を冷やしていると、いつも熱く感じます。
このループに入ると気づけば常に胃腸が冷えている状態になってしまうのです。
このタイプは汗かきさんが多いのも特徴です。
それも「脾」が弱っているからなのです。
出過ぎる汗を引き締めるのも「脾」が作る引き締める力
「脾」は食べたり飲んだりしたものから栄養を作りだし、それを体の隅々まで運びます。
その時できるものが「気血津液」と言われる体の構成要素。
「気」とは目に見えませんが、誰でもが持っている生命力や臓器を動かす力などを言います。
気は体のバリア機能や、各内臓や脳、手足をしっかり働かせる原動力です。
十分に無いと出てはいけないものを漏れ出させてしまうというのが「気」の重要な働きの一つ。
これを中医学では「固摂(こせつ)」と言います。
固摂作用が働かないのは、「気」がしっかり働いていないから。
そして、汗がなかなか止まらないのです。

汗は、体温を下げるために出るものですよね?
口の中、喉、食道を通る時、スーッと涼しく感じるけれど、冷たい飲み物や食べ物で、体にこもった熱を下げられたなら本来そんなに汗はでないはず。
汗が出て止まらないのは、汗と一緒に「気」も体から出て行ってしまうからだと考えられています。
なので、汗は必要以上にかき過ぎない方がいいのですよ。
要らない水分は、尿や便で出す。
しっかり「脾」が働いていたら、それができるはずなのです。
こういう体のメカニズムを解剖しないで(どこかのタイミングではやっているとは思うのですが)たくさんの人を検証しながら、築き上げてきた中医学なのです。
頬のたるみやほうれい線が目立つなら「冷たいものを止める」こと。
そして、脂っこいもの、甘いもの、コッテリした味付けのものも「脾」を弱らせるのでほどほどに。
ほうれい線対策におすすめの食べ物
ほうれい線対策に止めた方が良い食べ物を書きましたが、おすすめの食べ物もあります。
それはまず「脾」が元気になる食べ物です。
色で言うと、黄色いもの。かぼちゃ、とうもろこし、大豆、栗、さつまいもやじゃがいもなどの芋類などです。
そして、砂糖によるものではなく天然のほっこりとした甘い味のあるもの。上に挙げた黄色い色のものがほとんどこの甘い味になりますね。
そして、筋肉を作るたんぱく質は欠かせません。
大豆たんぱくでも良いのですが、薬膳には「同物同治(どうぶつどうち)」の考え方があり、これは「ある部位のためにはその部位を食べるとよい」というもの。
つまり、お肌のためには皮付きの肉を食べると良いということになります。
鶏の皮付き、豚の皮付きなどですが、一番手に入りやすく馴染みがあるのは鶏だと思います。
なので、鶏肉の皮も一緒に食べるようにしましょう。
その他皮膚のヒアルロン酸など潤いの素になる物を食べると良いですね。
これには、薬膳では白きくらげが有名です。

庶民のツバメの巣と言われるほどの潤い効果があると言われているものです。
最近は、国産のフレッシュな白きくらげも比較的簡単に買えるようになりました。
主張する味ではないので、いろいろな料理に使えます。
乾燥状態の白きくらげは、一度水戻し短時間茹でて歯ごたえのある状態でサラダや餃子に入れたり、味噌汁、スープ、煮込んでポタージュなど使い道も多いきのこです。
ほうれい線対策とおすすめの食べ物まとめ
中医学では、五臓の「脾」の弱りから頬のたるみやほうれい線が目立つようになると考えられています。
「脾」を弱らせるのは冷たい食べ物・飲み物と揚げ物などの脂っこいもの、砂糖を使った甘いもの、コッテリしたものです。
これらを減らして、「脾」を元気にする黄色ぽいもの、天然のほっこりしたものの他に、たんぱく質を摂ることも大切です。
その中でも、時々は皮付きの肉、そして潤わせる白きくらげを摂るように心がけてみてください。
【関連記事】
毎日水3リットル飲むダイエットや健康法をやってはいけない7タイプの人






