月子(ユエズ)とは、出産後6~8週間の産褥期と言われる期間に、中国、台湾、香港や韓国などの国で昔から続く産後ケアです。
妊娠から出産を経験した女性の体は、全治1か月とも2か月とも言われるケガに例えられるほどダメージを受けています。
出産後6~8週間の期間に、産後の女性の心と体の回復をはかる習慣が月子(ユエズ)。
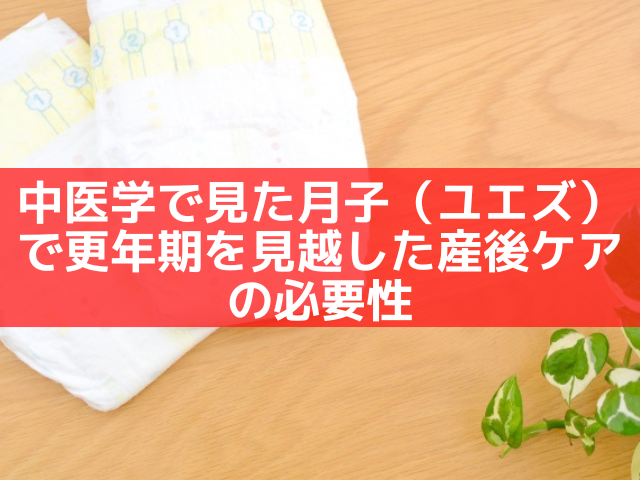
現代社会では、そこまで厳格にしなくても!と感じるものもありますが、中医学の視点からはとても理にかなっています。
日本の女優さんが韓国で出産後に産後ケアセンタ―で過ごしたり、数年前にオリンピックの卓球選手が台湾での出産後に体験されたことが知られています。
ただ、そんな習慣の根付いた地でも、昨今、都市部を中心として共働き夫婦が当たり前になっていることや、収入減を避けるために産後2週間程度で職場に復帰する女性もいると言います。
また、日本でも産後ケアに目が向けられ、令和三年母子健康法が改正され、自治体でも産後の母体ケアを積極的に取り組む動きがあります。
様々な産後ケア関連のサイトを見ていて気になるのは、産褥期の母親の心身の回復と育児指導が産後ケアの定義にあるように、女性の健康のほんの一瞬だけしか考えられていないかのようなものも見受けられることです。
出産は終わりではなく、通過点。女性の人生の次のステージが始まります。
日本女性の平均閉経年齢が50歳(公益社団法人 日本産科婦人科学会より)。
個人差がありますが仮に30歳で出産しているとすれば、子供が20歳前後で閉経。更年期はその前後各5年の45歳~55歳となります。
この頃であれば、子育ては一段落しているでしょう。
ところが、「高齢出産」と言われる35歳以上で初めての出産を経験した場合や二人目以降を40歳以上で出産した場合は、子育て中に更年期障害が起こることもあり得ます。
高齢出産する女性の増加から、高齢出産した人こそ産後ケアをし、その後の子育てが健康的で望むべきものとなるよう、月子(ユエズ)の意味を中医学の視点から解説します。
私自身が、39歳になる手前で第一子を出産し、子育てが更年期障害と並行だった経験から、高齢出産した人にこそ月子(ユエズ)の考え方を知っていただけると幸いです。
月子(ユエズ)とは
月子(ユエズ)とは、中国・台湾・香港などの中華圏と・韓国で伝統的に行われている産後1か月の伝統的な産婦ケアです。
産後の女性は、
・風に当たってはいけない
・体を保温
・冷たい飲み物食べ物は禁止
・水に触ってはいけない
・入浴、洗髪、手洗い、歯磨き禁止
・月子食を食べる
・目を使うことは禁止
・家族(産婦の母、姑、夫)以外は産婦の部屋に入ってはいけない
などの伝統的な決まりに乗っ取り、産婦は食事と授乳とトイレ以外は横になって過ごす産後1か月の産後ケアを言います。
お姑さんにお世話をしてもらう人もいれば、月子センター(月子中心)という産院隣接のホテルのような施設に入り、産後の体を元に戻し新生児は専門のスタッフがケアしてくれるという産後の習慣です。
かつては夫の実家に滞在し姑に面倒を見てもらうのが主流だったようですが、現代では月子センターに入るか、月子期間中にユエサオという専門の家政婦兼ベビーシッターに自宅に来てもらうという選択肢もあるとのことです。
月子(ユエズ)期間の決まりの中で、入浴・洗髪・手洗い・歯磨きが禁止と言うのは現代では受け入れがたいことではないでしょうか。
昔は、衛生的ではない水からの感染や暖房が十分でない時に洗髪し体を冷やし風邪をひくことを避けるようにと言う理由があったのではないかと考えられます。
冷たい食べ物や飲み物を避ける考え方は中医学では普通に言われることです。
冷えと湿気に弱い消化器系のシステムに当たる「脾」を弱らせて、母体の回復を遅らせたり母乳に影響がないようにする考えでしょう。
また、妊娠から出産までの期間にダメージを受けるのは「腎」ですが、「腎」は冷えに弱い特性があります。
「腎」は人の老化とも深く関係するため、体は保温して風に当たらないようにという教えとなったのでしょう。
出産後には、細かい文字を見たり目が疲れることをしないようにとは日本でも言われていることです。
これは、妊娠中から授乳期間は、体の構成要素の一つである「血(けつ)」を消耗しているからです。
目を使えば使うほど血(けつ)を消耗するので、目を使うことを禁止しているのです。
母乳も血(けつ)が変化したものと考えるので、目を酷使していると母乳の量にも影響すると考えます。
特定の家族以外は産婦の部屋に入ってはいけないというのも、昔は外からの邪気(現代のウイルスや細菌なども指す)が産婦や新生児に影響しないための考え方でしょう。
月子食はいわゆる薬膳になります。
目的は、ダメージを受けた「腎」の回復と日々、母乳で失われる血(けつ)を補うものが中心のスープやご飯などをバランスよく作られます。
実際に、中国で月子(ユエズ))を体験した日本の女性によると、8時の朝食、10時のおやつ、12時の昼食、15時のおやつ、18時の夕食、20時の夜食と1日6食出されたそうです。
高齢出産に産後ケアが特に必要な理由
このような産後ケアですが、高齢出産をした後こそしっかりとしたケアが必要です。
産院から退院した当日から家族のために家事全般をしたり、上のお子さんの幼稚園の送迎などをしてしまうと「腎」がしっかり回復しないまま、更年期に入ってしまう可能性があるからです。
出産はゴールではなく、そこからが子育てのスタート。

自分の体が元に戻っていなくても子育てに待った!はありません。
中医学では、「腎」に蓄えられている「精」というその人の持つ生命力の源のようなものは年齢と共に減少し、妊娠や出産で更に減少して行くと考えます。
「精」から血(けつ)も作られるため、減少した状態では、血(けつ)不足も免れません。
血(けつ)は栄養を体の各システムに運び、潤わせる働きを担うだけでなくメンタルにも影響します。

その結果、子育て中のイライラが強くなったり、鬱っぽくなる可能性に繋がるのです。
高齢でなくても、出産後には「腎」を立て直し、体のケアと心のケアをするために産後ケアは重要ですが、更年期まで考えると特に高齢出産後の産後ケアはおろそかにはできないのではないでしょうか。
更年期まで考えた高齢出産した人のための産後ケアを!
高齢出産する人の中には、長年キャリアを積み、出産後も早めの社会復帰を望むケースが少なくないことが想像できます。
望んで来た出産を経て、その経験からも社会貢献できることはこれからの日本にとっても大切だと考えます。

経験豊富で優秀な人材が、更年期と子育ての板挟みとなりキャリアを断念しなくて済むように、現代医学のケアだけでなく中医学の面からのアプローチが産後ケアにあっても良いのではないでしょうか。
台湾の産後ケアを経験された方によると、月子センターには小児科医・看護師・中医が常駐し毎日の回診があり、これからの子育てのための母親学級が受けられると言います。
そして、月子食は当然付きます。
今後、日本の産後ケアセンターでも、中医学の考え方も取り入れ「腎」のリカバリ―とその先の更年期まで見据えた月子(ユエズ)のような産後ケア施設ができることを願います。
高齢出産の方は更年期まで見据えた産後ケアセンターを選択することをおすすめすると同時に、出産という女性の一生の一つの事象だけでなく長い目でケアしてもらえる施設の増加が、女性の生涯にわたる健康と子育て支援の一つになるのではないかと考えています。
【参考】
母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第 69 号。産後ケア事業について定めるもの。)に関するQ&A
妊婦の高齢化に伴い、人気が高まる産後のケア施設。今後のニーズは?
〈論文〉現代中国都市部における産後の養生「坐月子(ザオユエズ)」近大と伝統の葛藤
【関連記事】






