
女性は冷やさない方が良いと言われ、よもぎ蒸しに興味を持たれる方もいらっしゃると思います。
ですが、よもぎ蒸しが合わない人、また合わないわけではないですが注意が必要な時もあります。
よもぎ蒸しが合わない人の特徴と注意点を知って、よもぎ蒸しをしてよかったと思えるようにこの記事を参考にしてください。
まず、よもぎに対してアレルギーのある場合は避けた方が良いです。
よもぎはキク科なので、キク科の植物に対するアレルギーのある場合も避けておいた方が無難ですね。
何らかの疾患があり、医療機関を受診中の場合は、医師と相談の上よもぎ蒸しをすることもおすすめします。
以上に加えて、ここでは、中医学と薬膳の視点からよもぎ蒸しが合わない人を4タイプに分けました。
目次
よもぎの特性
よもぎは、餅や団子などに練り込まれ日本人には食べ物に使うことで馴染み深いものですが、漢方の本場、中国では艾葉(日本での読み方は「がいよう」)と言われ薬として使われるものでもあります。
よもぎの葉を煎じて飲んだり食べることで冷え性の人や冷えから来る痛みなどによいとされ昔から女性の不調に使われて来ました。

よもぎの葉は裏が白いのが特徴
よもぎ蒸しは、温める性質を持つよもぎを乾燥させ、それを煎じた蒸気を下半身の粘膜から吸収させるというものが一般的です。
よもぎの温める性質と効果を、食べるのではなく粘膜から吸収するのがよもぎ蒸しになります。
温める性質を温めて吸収させるので合わない人もいるのです。
よもぎ蒸しが合わない人を4タイプに分ける
よもぎ蒸しが合わない人を大きく分けると次の4タイプになります。
1. 潤い不足の人
2. 貧血気味の人
3. 疲労している人
4. 炎症・発熱などの熱の症状のある人
潤い不足の人とは、アラフィフ世代以降に多い陰虚のタイプとなります。
疲労している人とは、病み上がりや、運動の後、気温が高く汗をかいた後などです。
貧血気味の人とは、睡眠不足が続いていたり爪が割れやすい、髪がパサつく、よく足がつるなどの人になります。
炎症がある人とは、皮膚が赤くなっていたり喉が痛いなど熱をこもらせていたり、発熱している人です。
潤い不足の人
アラフィフ世代の多くは潤い不足の陰虚と言われる状態になります。
陰虚になると、顔の火照り感や顔や頭が暑くて周りは汗をかいていないにも関わらず、自分一人だけ汗が流れて止まらないと言う状態になることがあります。
中医学では、陰虚は陰と陽のバランスが崩れ、陰が減少したために相対的に熱の性質である陽が強まってしまった状態。
他にも、手や足が熱くて布団から出さないと眠れないとか、日中は元気なのに夕方頃からなんとなくだるくて熱っぽく感じることもあります。

足は冷えるのに顔や頭だけが暑くなる
体の中で熱を冷ます水が少ないために冷やすことができないのです。
陰虚の人がよもぎ蒸しで体を強く温めて大量の汗をかくと、更に潤い不足の状態に!
眠れなくなることもあるので、陰虚の人は短時間にするか、じんわり温める程度に止めておくようにしましょう。
よもぎ蒸しの前や途中に水分補給も忘れずに。
貧血気味の人
貧血と言っても数値で貧血と出ていない人も含みます。
中医学では数値に出ていない人でも、髪がパサつく、爪が薄くてすぐ折れたり二枚爪になりやすいなどの爪トラブル、髪の毛がパサついたり枝毛や切れ毛などの髪の毛のトラブル、脚がつりやすいなどは血虚の症状になります。

血(けつ)は体の構成要素の「気・血・津液」の一つ。
液体なので、血(けつ)が少ない血虚でも潤い不足になります。
血虚の人がよもぎ蒸しで強く温められると、血液がドロドロになり頭痛がしたり血圧が上がったりすることがあります。
なので、血虚の人はよもぎ蒸しはおすすめしませんし、普段はよもぎ蒸しを受けている人も睡眠不足が続いて血が作られにくい時は止めておいた方が無難です。
血虚の人はまず、毎日23:00前に寝るように心がけ、赤みの肉やレバー、なつめなどの赤い色の食べ物を食べて血(けつ)を補うようにしてください。
血虚はそのままにしていると陰虚に移行して行きやすいので、常に気をつけたいものです。
疲労している人
中医学では疲れている状態を気虚と言います。
気は目には見えませんが、元気・気合・覇気など体のパワーを表す言葉にも使いますよね。
気は体のバリアを張ったり、体温維持、各臓器をスムーズに機能させるなどの働きがあります。
食事で食べた物や呼吸によって得ることができますが、消化器系が弱い人は気を十分に作りにくいのです。
そのため、少し動くと疲れてしまったり食後に眠くなったりします。
中医学では、気は汗と一緒に出て行ってしまうと考えます。なので、よもぎ蒸しに限らず大量に汗をかきすぎないようにします。
風邪をひきやすい人、お腹のが弱い人、病み上がりは気虚の状態ですし、運動で汗をかいた後や夏の日中に汗を大量にかいた後などはすでに気が減っている状態なのでよもぎ蒸しはおすすめではありません。
炎症・発熱など熱の症状のある人
皮膚が赤く熱を持っていたり、喉が痛いなどの炎症がある時は体に熱がこもっている時です。

発熱している時にエステティックサロンには行かないと思いますが、自宅によもぎ蒸しがあったら早く汗をかいて熱を下げたいと思うかもしれません。
体に熱がある時によもぎの温める性質に加え、蒸気で熱を加えると痒みや赤み、炎症が増すことが考えられます。
発熱したばかりだと汗は出ずにさらに熱が上昇してしまいます。
皮膚や喉の痛みなど体のどこかに炎症がある時はよもぎ蒸しは控えた方が良いですね。
よもぎ蒸しが合わない人もいるという知識のあるサロンで受ける
このように、4つのタイプに当てはまる場合、合わない人や普段は問題なくても控えた方が良いタイミングがあります。
自分で判断することが大切ですが、よもぎ蒸しの良いところだけに着目するのではなく知識があって信頼のおけるサロンで受けることが重要だと考えます。
受ける時には、汗をかきすぎない温度で時間を調整してもらえたり事前にしっかり今日の体調やもともとの体質などをカウンセリングして、時にはよもぎ蒸しを控えることを提案してもらえるサロンが安心ですね。
よもぎ蒸しやサウナなどで汗をかく場合には適度に水分補給も忘れないようにしましょう。
【関連記事】
-
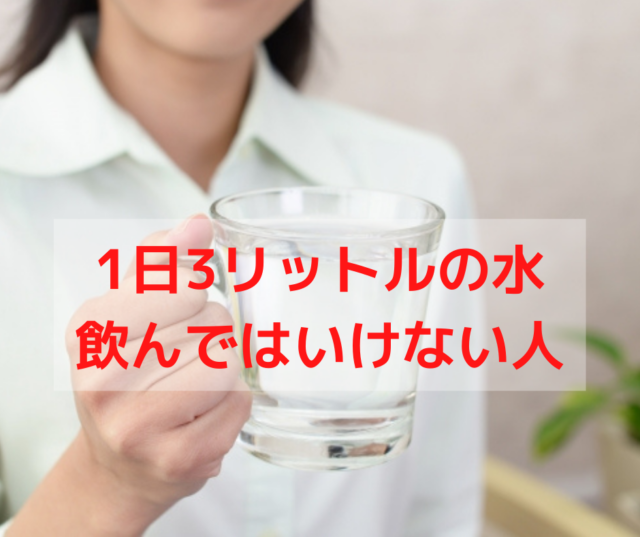
-
毎日水3リットル飲むダイエットや健康法をやってはいけない7タイプの人
タレントや芸能人が推奨している1日に水を3リットル以上飲むダイエットや健康法は誰にでも合うわけではありません。 彼らは、健康面と運動面でパーソナルトレーナーの指導を受け、その中に3リット ...
続きを見る
-

-
薬膳と漢方の違いと関係
薬膳という言葉が広まる前から、漢方や漢方薬という言葉は聴いた事があると思います。 薬膳と漢方の違いや関係についてお伝えします。 目次1 発祥は中医学(中国伝統医学)です2 中医学と漢方の ...
続きを見る






