気温が上がり蒸し暑くなる日本の夏にお子さんが部活でパフォーマンスを上げるためにはどんな食事とドリンクを与えたらよいのかは、スポーツをするお子さんを持つご家庭では気になるところです。
ここでは、薬膳の視点から、夏の部活でパフォーマンスを上げる家庭でできる食事とドリンクについてお伝えします。
目次
夏の季節的特徴からパフォーマンスアップを考える時最も気をつけるのは五臓の脾
日本の夏は湿気のある蒸し暑さが特徴です。
湿気は五臓の脾というシステム、つまり消化吸収排泄に関わる内臓を弱らせると言われています。
暑さと運動による発汗で失った水分補給は大切ですが、一度に大量の冷やしたドリンクを飲むことは胃がちゃぽちゃぽになり動きにくくなります。
そして、脾を最も弱らせる行為です。

アスリートに限らず人の体を作る素は飲食物です。
栄養学に基づいた食事をしていたとしても、消化器が効率よく動いて食事を栄養に変えなければ筋肉は作られず、トレーニングによって傷んだ筋肉の修復もできません。
なので、アスリートの食事やドリンクを考える時最も大切なことは消化器系に当たる脾を弱らせず効率よく栄養を吸収できるものにすることです。
アスリートは緊張から脾を弱らせやすい
普段の練習でもライバルに負けないように、レギュラーに早くならないと!などのプレッシャーがあるアスリート。
スポーツで一流を目指す方が勉強より大変だと言われるのもここです。
そして試合前、試合当日となると交感神経が高ぶり過ぎる人もいるかもしれません。
良い緊張は実力以上のパフォーマンスを発揮する原動力になりますが、少なくともストレスになることは間違いありません。
ストレスを感じて弱るのは五臓の肝です。
肝が弱ると、消化器系のシステムである脾を抑制するという五臓の関係性があります。
これは薬膳の基本となる中医学では良く知られていることで、緊張するとお腹が緩くなる、下痢をする、便秘になるなどがコレです。
試合は普段練習している場所ではないので、場所が変わることでストレスを感じることもあります。
旅行に行くことは嬉しいし楽しいですが、枕や布団が変わる、食事が家の食事と違う、などの「普段との違い」は体にとってはストレスに違いありません。
なので、旅行に行くと便秘になるというのも、肝→脾の抑制関係からの症状なのです。
では、脾を弱らせず、パフォーマンスアップさせる脾のケアを考えた食事とドリンクはどんなものになるのでしょうか?
アスリートがパフォーマンスを上げるための夏の薬膳の目指すところ
脾を弱らせないためにして欲しいこと、おすすめの食材の順に書いて行きます。
脾を弱らせないためには次の4つに気をつけます。
1.氷を入れてキンキンに冷やしたドリンクやアイスなどを控える。
2. 揚げ物や大量の脂の多い肉などを控える。
3. 甘いお菓子、甘い菓子パン、甘いジュースや炭酸飲料などを控える。
4. 味付けの濃いコッテリしたものを控える。
おすすめするものは、脾を強くするとされる食材です。
1.黄色いもの・・・とうもろこし、かぼちゃ、大豆、さつまいも、じゃがいも、栗など
2.天然のやさしい甘味のあるもの・・・上に挙げたものと米がこれに当たります。
3.和の発酵食品・・・味噌、納豆、甘酒、ぬか漬けなど

最初に脾は湿気に弱いと書きましたがこれらの中でも豆類は脾を守るだけでなく、湿度や脾を弱らせないための1~4を摂ってしまった時にもおすすめです。
冷たいものや脂っこいもの等を常に続けて摂っていると、脾が弱り水分代謝が悪くなるため、お腹を壊しやすくなります。
すると、せっかく食べた物が栄養に変えられずにそのまま便として出てしまったり下痢をしやすくなるので、食べても筋肉がつかない、パワー不足などになる可能性があります。
発酵食品にはチーズやヨーグルトも入りますが、日本人には和の発酵食品がおすすめです。
腸の善玉菌を増やし腸内環境を良くすることで消化吸収排泄がスムーズにできる体にして行くことができるからです。
このように、控えるものとおすすめのもので脾を強くすることをベースとするのが、アスリートがパフォーマンスを上げるための夏の薬膳の目指すところとなります。
アスリートのパフォーマンスを上げるための目的に合わせたおすすめ食材
脾を整えながら、次に目的に合わせた食材を摂って行きます。
■パワーをつける(補気)
パワーとは中医学の用語で「気」となります。
気は目に見えないものですが、人が生まれた時にはすでに誰でもが持っています。
呼吸をするのも、体温維持できるのも、病気にならないためのバリア機能も、食べた物を栄養に変えて不要になったものを排泄するのも全て「気」が担っています。
つまり、普通の暮らしをしているだけでも気は消費されているのです。
その上、激しい運動をするアスリートは意識して気を補う必要があることは言うまでもありません。
気を補う食材は、脾を強くする食材と重なります。米、とうもろこし、かぼちゃ、芋類、豆類などです。
ここに、玉子、鶏肉、豚肉、きのこ類が入ります。
減量が必要なスポーツで、カロリーは控えめにしつつ気も補えるのがきのこ類になります。
きのこと鶏むね肉のソテーやマリネなどがおすすめです。
■筋肉をつけケガをしにくくする(強筋骨)
関節の曲げ伸ばしがスムーズになる、骨を強くする、筋肉をつけるなどの目的であれば強筋骨という効能を持つ食材がおススメになります。
牛筋、鹿肉、馬肉、牛肉全般などの肉類と骨付き肉のスープです。
薬膳には体のある部位を強くしたければ、その部位を食べるという「同物同治」の考え方があります。
つまり筋肉を増やしたければ筋肉を、骨を強くしたければ骨付き肉のエキスを煮出したスープ、軟骨などとなります。
もちろん、小魚でも構いません。
イワシやカタクチイワシの稚魚ちりめんじゃこなどもカルシウムが豊富なのでおすすめです。
傷んだ筋肉の修復にはたんぱく質が必要です。
■筋肉を滑らかでスムーズに動かす(補血)
作った筋肉が硬く滑らかに伸び縮みしなければケガをしてしまいますよね?
筋肉をスムーズに動かすためには、食べた物から作られた栄養を運ぶ血が必要です。
練習中に良く脚がつる人は、血が足りていない可能性があります。
試合前のきつい練習で血が失われたまま補給できず試合当日を迎えると、試合中に脚がつることもあります。
特に、中学生高校生の多感な時期だと、試合前日に緊張や興奮でよく眠れないこともあるでしょう。
中医学では血は23:00~3:00に作られると言われます。
なので、試合当日に脚がつる場合は睡眠不足や試合までの過労も考えられます。
適切な時間に睡眠をとることと血を増やす食材で脚がつるのは避けられます。
血を増やす食材は、牛の赤身、マグロやカツオなどの赤身の魚、レバー、イカ、タコ、あさり、黒豆、黒ごま、黒きくらげ、ほうれん草、にんじん、ぶどうなどになります。
わざわざアスリート向けの特別食でなくても、レバーニラいため、あさりの味噌汁、黒豆入りご飯、ほうれん草と黒きくらげの卵とじなどでも補血メニューです。
■ストレスを解消する(理気)
緊張を和らげたり溜まったストレスを解消するには香りの良いものと酸味を使います。
柑橘類、柑橘類を使ったドレッシングやサラダ、紫蘇、三つ葉、セロリ、パセリなど香味野菜がこれに当たります。
また、鰹だしの香りなどは日本人の究極のアロマとも言われ、緊張を緩める効果もあると考えられます。
糖質オフはアスリートの持久力をダウンさせる
糖質オフダイエットが言われるようになってから、ご飯を止めておかず中心の食事の方が良いと考える中高生もいるようです。
ところが、日本スポーツ協会によるスポーツ栄養のPDFのよると、持久力を上げるためには肝臓に溜められているグリコーゲンがエネルギー源として使用されると書かれています。
強度の高い筋トレは、グリコーゲンが消耗されるためトレーニング後は糖質の補充が欠かせません。
なので、アスリートの持久力向上には糖質オフは不向きです。高強度のトレーニング後にはおにぎりなどで糖質をすばやく補充することが大切です。
また、糖質をエネルギー減に変える時、ビタミンB1が使われます。ビタミンB1が多く含まれるのは豚肉や、大豆食品などです。ビタミンB1の欠乏があると最大酸素摂取量を低下させると言われています。
血中酸素が不足になればパフォーマンスが下がるのは当然です。
アスリートの食生活には炭水化物と豚肉などのビタミンB1が多く含まれる食材を加えましょう。
夏の部活で水分補給におすすめなもの
体液濃度と同じスポーツドリンクが当たり前になっています。
激しい運動で失われた水分を効率よく補給するには効率的だと思います。
けれども、砂糖が気になるようであれば、冷たい水より素早く喉の渇きを癒すことができ、体にこもった熱を冷やすことができるものがあります。
それはキュウリやスイカ、トマトです。
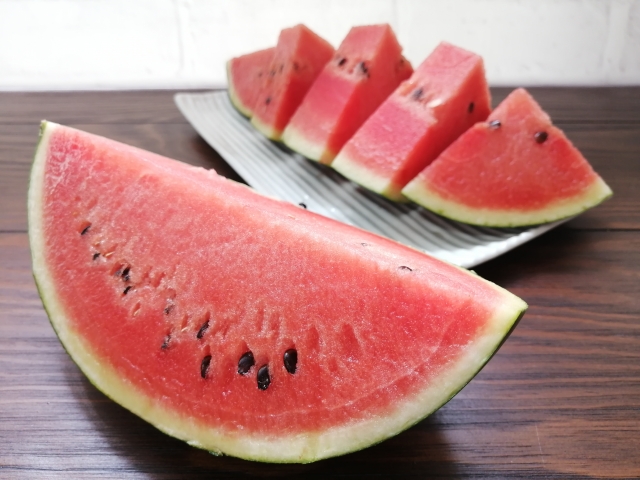
夏が旬のものは体の熱を冷やす性質があり、たっぷりの水分は水より分子が小さいためすばやく細胞に吸収されると言われています。
なので、練習時にはスイカやキュウリを一口サイズに切ったものやプチトマトを持っていくのもおすすめの方法です。
または、練習から帰ったらキンキンに冷えた麦茶より、すいかやきゅうり、すいかジュース、トマトジュースなども良いですね。
これらは常温でも体を冷やすため、キンキンに冷やしたドリンクで脾を弱らせることも減らせます。
夏の部活でパフォーマンスを上げるための食事とドリンク
中高生の夏の部活でパフォーマンスを上げるには、家庭の食事が大切です。
中でも一番大切なのは、冷たい飲み物食べ物で消化器系を弱らせないことです。
脾を弱らせる食べ物は控え、丈夫にさせる黄色い食材、天然の甘みのある食材を中心に和の発酵食品も取り入れます。
パフォーマンスを上げるための目的合わせながら、バランスよく食べること。
糖質オフや睡眠不足にも気をつけながら、家族と極端に違うものを食べさせるのではなく普段から目的や効果を伝えながら食べさせることで親子で夏のパフォーマンスアップをはかってください。
【関連記事】






