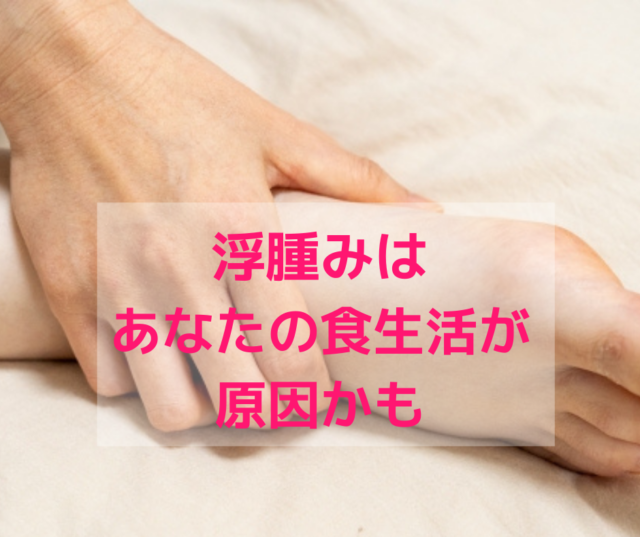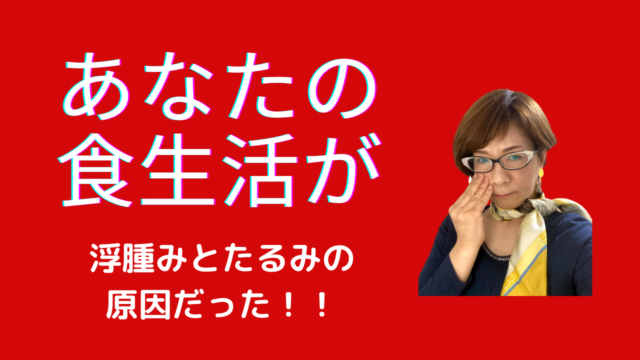浮腫みの原因が、胃腸の弱りだと言ったら驚かれるかもしれませんね。
薬膳の基になる中医学では、消化器系を担当している働きに名前が付いていて「脾」と「胃」がそれに当たります。
脾と胃が弱ると要らない水分を溜めやすい体になると中医学では言われています。
ここでは、浮腫みの原因と対策を薬膳の視点からお伝えします。
目次
むくみの原因となる食事前のこんな習慣
脾と胃は冷たいものと湿気に弱いことが言われているのですが、考えてみてください。
私達は、どれだけ冷たいものを飲んだり食べたりしているかということを。
外食をしようとレストランに入ると、冬でも氷入りの冷たい水が提供されます。
これは日本ならではのお店からのサービスなのですが、できれば常温もしくはお白湯であれば脾と胃のためになるのです。

真夏はついつい飲み干してしまいますが・・・
これから胃に入って来る食べ物を消化する前に、氷入りの冷たい水を一気に飲み干したらどうなるでしょうか?
胃液が薄まり、胃が冷えます。
胃液が薄まれば消化能力が落ち、もともと冷えに弱い胃がうまく働かなると思いませんか?
初めにして欲しいことは、食事の前に冷たい飲み物を一気に飲み干さないということです。
浮腫みの原因は脾の弱り!脾を弱らせる3つの食べ物
食事の前に、冷たいドリンク類を飲まなかったとしても、脾を弱らせる食べ物があります。
肥甘厚味(ひかんこうみ)と言われるものです。
「肥」とは脂っこいもの、「甘」とは砂糖を使った甘いもの、「厚」とはこってりしたもの。
これらを頻繁に食べていると脾が弱ると言われているのです。
具体的に言うと、揚げ物、スイーツ類、揚げ物や肉の脂身を使ったものを甘辛い味で絡めたりとじたりしたものということになりますね。

たまには良いのですが頻繁に食べるのは脾を弱らせます。
その他にも、頻繁に大量の乳製品を摂ったり、アルコールを摂ることも脾の負担だとされています。
脾と胃は表裏の関係を持ち、どちらかが弱るとすぐもう片方も弱るので、「脾胃」と一緒に呼ばれることが多いです。
つまり、冷たいものと肥甘厚味のもの、常に食べる乳製品、大量のアルコールは消化器系を弱らせる飲食物ということです。
これらがなぜ、消化器系を弱らせ浮腫みの原因になるのかというと、脂肪は消化に時間がかかり、砂糖は体に湿気を呼び込むからです。
脾を弱らせる浮腫みの原因には大量のフルーツや消化の悪い玄米も含まれる
スイーツが脾を弱らせて浮腫みの原因となるのなら、スイーツではなくフルーツなら良いのかというと食べ過ぎはやはり浮腫みの原因となります。
なぜなら、フルーツの多くは体を冷やす性質を持ち、冷蔵庫から出したばかりのフルーツはたっぷり含まれる果汁が脾と胃を冷やすからです。

女性が好きなものは浮腫みやすいものが多いですね涙
また、健康志向から白米を止めて玄米を食べるようにしている人も多くなってきました。
もともと消化能力が弱い人は玄米を消化するのに時間がかかり、消化器系の負担となります。
栄養学的に見た浮腫みの原因
ここで、栄養学的に見た浮腫みの原因も見てみましょう。
まず思い浮かぶのは塩分の摂り過ぎではないでしょうか?
体内のナトリウム濃度は一定に保たれています。
塩分を摂取するとナトリウム濃度が上がるため、喉の渇きを覚え水分を摂ることで(水で薄めて)ナトリウム濃度を元に戻すのです。
カリウム不足も浮腫みの原因になります。
カリウムはナトリウムと結合して体外に排泄するのを助けます。
野菜や海藻類などをあまり食べない人はカリウム不足で浮腫みやすくなることがあります。
アルコールの飲み過ぎも浮腫みの原因になります。
アルコールは利尿作用が高いので体内が脱水症状となり、さらに水分を摂ることで浮腫みの原因となります。
血中アルコール濃度が高まり血管が拡張することで血漿が漏れ出して細胞内に留まるからとも言われます。
薬膳の視点から浮腫み予防をする方法
冷えと湿気に弱い脾胃を守るために、冷たいものを避けることから始めてみましょう。
特に食事の前に冷たい水を飲まないことです。
次に、今もし頻繁に肥甘厚味の食べ物を好んで食べているとしたら、それを控えめにすることです。
脾胃を元気にするには、さっぱり食べられる消化のよいものを温かい調理法で食べるのがおすすめです。
そしてここに、水分代謝を促す豆類やとうもろこしの髭、はと麦などを加えます。
夏ならきゅうりや冬瓜、すいかなどの瓜類もおすすめです。
瓜類は、必要な水分は補い浮腫みの原因となる不要な水分は排泄させるからです。
野菜は全般的にカリウムを多く含みますが、里芋は特に多く胃腸の調子を整えて要らない水分を出す効能があるとされます。
果物にもカリウムは多く含まれますが、身体を冷やすものが多いので摂り方に工夫が必要です。
例えば、最も多く含まれると言われるバナナも冷やす性質なので、電子レンジで少し温めるとか焼きバナナにする、温める性質を持つシナモンパウダーをかけるなどしてなかったことにする薬膳{※)の方法で食べます。
(※)なかったことにする薬膳は、その食材の持つ効能や性質を利用したいのに、不要な体への影響がある場合に調理法や食材の組み合わせで影響を緩和させる薬膳の知恵です。
玄米を含む雑穀類はミネラルと食物繊維が豊富で、生活習慣病予防には摂りたい食材の一つですが、玄米は胃腸機能が弱い人には消化に時間がかかるためお腹が痛くなったり下痢を招くこともあります。
負担を減らすためには、炊く前の浸水時間を長めにして柔らかめに炊いたり、発芽玄米を使うなどで消化に負担のない工夫もしてみてください。
浮腫みの原因と対策
薬膳で浮腫みの原因を挙げるなら、消化器系にあたる脾胃の弱りです。
脾と胃は冷えと湿気に弱いため、まず冷たいものを止めることが最優先になります。
次に肥甘厚味のものや乳製品を控えめにしてさっぱりとした消化の良いものを温かい調理法で食べることです。
特に雨の日、雨の降る前日などはこれを心がけてください。
天気の影響で湿気が体に入ると浮腫みの原因となりやすいためです。
塩分の摂り過ぎ、アルコールの摂り過ぎに気をつけてバランスよく野菜や海藻類なども食べます。
フルーツには塩分に含まれるナトリウムを排泄させるカリウムが多く含まれますが、フルーツの多くは冷やす性質なので食べ方に注意が必要です。
玄米は消化に時間がかかるため、消化器系が弱い人は炊き方に気をつけて発芽玄米などを使ってみてください。
【関連YouTube動画】
【関連記事】
毎日水3リットル飲むダイエットや健康法をやってはいけない7タイプの人