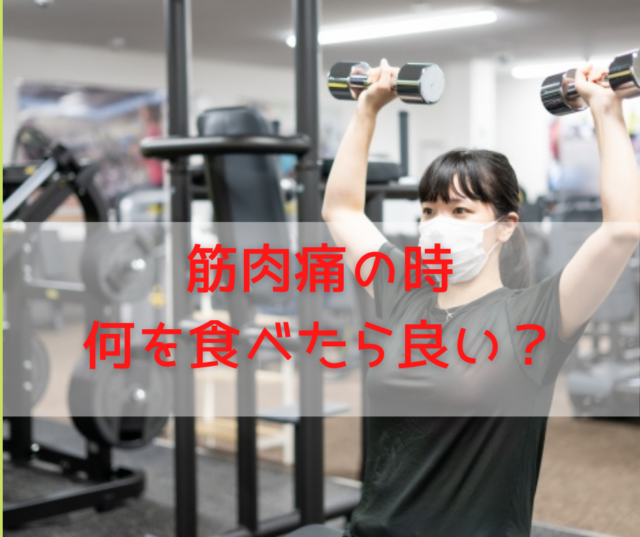寒い冬は運動するのを控えていた方も、春から運動を始めようかと思っている方も久しぶりの運動の後は筋肉痛の心配があると思います。
筋肉痛は筋繊維が運動によって傷つき修復する時に起こる炎症だと考えられています。
これを早く回復させたり少しでも予防するためには食べるものも関係します。
ここでは、筋肉痛の回復と予防におすすめの食材を薬膳の視点からお伝えします。
筋肉痛の種類と原因を中医学で考える
筋肉痛は大きく分けると二種類になります。
1.運動している最中や直後に起こるもの・・・即発性筋肉痛
激しい運動をすると筋肉に負荷がかかり緊張状態が続くと、血液循環が悪くなります。
すると、酸素不足となり筋肉痛が起こるというものです。
2.運動して数時間後から数日後に起こるもの・・・遅発性筋肉痛
一般的に筋肉痛と言われるものは、遅発性筋肉痛です。
若い時は翌日起こるのに、年齢を重ねると遅れて出ると言われることもありますが、その根拠は医学的にははっきりしていないものです。
普段あまり運動をしていない高齢者は、毛細血管が発達していなかったり血管の弾力性が弱り筋繊維の修復に時間がかかると考えられます。
筋肉をゴムのように滑らか伸縮させるのは、体の構成要素である「気血津液」の内、気と血だと言えます。
臓器が本来の働きを十分にできるのも、血や津液がスムーズに流れるのも気の力であり、筋肉への栄養となるのは血だからです。
中医学で考えると、筋肉痛の起こるメカニズムは気が減少して血の流れが悪くなり、栄養が十分でなくなるために起こると考えられます。
筋肉の動きに関わることで言えば、他にもこむらがえりや脚がつる、瞼がピクピクするなど自分で制御できないことは血の不足と言えます。
筋肉痛の時に何を食べると良いのか
気と血を増やすことが大切なので、筋肉痛の時は、気を増やすもの、血を増やすもの、血を流すものの中でも強筋骨効果のある、イワシ、カタクチイワシ、ウナギ、牛肉、牛すじ、馬肉、うずらの玉子などがおすすめです。
特に、薬膳の考え方には同物同治(どうぶつどうち)があります。
これは、肝臓を良くしたかったら(肝臓)レバーを食べ、心臓を良くしたかったら(心臓)ハツを食べるというものです。
なので、筋肉や筋を良くしたかったら牛すじがおすすめなのです。
また、食材の性質には、それを食べると体が温まるもの、冷えるもの、どちらでもない中間のものがあります。
これを考えた場合、血を巡らせるためには冷やすのではなく温めて流します。
ここで挙げた食材の中では、イワシ、カタクチイワシ、牛すじが温め食材で、ウナギ、うずらの玉子は温めも冷ましもしない食材になります。
温めも冷やしもしない食材はは摂らない方が良い訳ではなく、できれば温める性質を持つ、生姜、にんにく、ねぎ、唐辛子などと一緒に摂ることで更に効果が増します。
そして、血を増やす食材と、巡らせることができる食材を摂ることも大切です。
血を増やす・・・黒豆・黒きくらげ・よもぎ・カシス・桑の実(マルベリー)・ぶどう・黒ごま・あなごなど
血を巡らせる・・・納豆・ニラ・菜の花・ブルーベリー・プルーン・イワシなどの青背の魚・酢など
砂糖の代わりにプルーンやレーズンを入れて牛すじを甘辛く煮たり、黒きくらげとニラを入れた牛肉の炒め物などがこれらの食材を合わせてできる献立ですね。
炎症なのに温める食材を食べても良いのか?
筋肉痛は、傷ついた筋繊維の修復時に起こる炎症と言いましたが、炎症なのに温めて良いのか?という疑問が湧くかもしれません。
激しい痛みと熱を持っているなら、温めるより冷やす方を選びます。
湿布も温める湿布と冷やす湿布があるように、熱を持っている時は冷やすのです。
そんな時におすすめなのが馬肉です。
馬肉は体を冷やす性質を持つ肉なので、通常はにんにくやネギなどの温める性質を持つ食材と一緒になかったことにする薬膳の方法で食べることが一般的です。
でも、熱を持つ筋肉痛の場合にはなかったことにする薬膳を使わずに、馬肉の冷やす性質を活かしながら強筋骨の効能をいただきます。
同時に消化器系の働きが落ちないようにする
せっかく血を作ったり流す食材を摂っても、それを消化吸収する消化器系がうまく働かなければ意味がなくなってしまいます。
なので、同時に消化器系にあたる脾が弱らないようにすることも必要です。
脾は冷たいもの、脂っこいもの、砂糖を使った甘いもの、コッテリしたもの、多量の乳製品、多量のアルコールで弱りやすくなるので筋肉痛の時はこれらは少し控えめにするようにします。
そして、強筋骨効果もある、山芋(長芋)、キャベツなどを一緒に食べるようにしてみてください。
山芋(長芋)は消化器系を整えるだけでなく体力・気力を補う食材です。薬膳では補気食材で疲れた時に一番最初に選ぶものと言っても良い食材です。
また、日本人の主食であるうるち米も体力・気力を補う最も身近で有効な食材だと言えます。
そして、消化機能をアップさせるために日ごろからよく噛んで唾液の消化酵素を加えた状態で胃へ送ることを心がけてください。
胃が喜びます!!
まとめ
食べ物は筋肉痛を治す薬ではありません。
治すのはその人の体に備わった力です。
それを補助するのが食べ物と考えれば、予防になるのも気と血を補い巡らせる食材となります。
基本は、温めて血の流れを促す食材を摂りますが、熱を持っている時は温めるより冷やします。
そして、忘れてはならないのは気や血を補う食材がしっかり消化吸収されるように消化器の働きを弱らせないことです。
日頃からこのことを気をつけて、なるべく筋肉痛が起こりにくく起きても早く元に戻せる自分の修復力をつけましょう。
トップアスリートでなくても運動する人の食事はおろそかにはできませんね。
運動中に汗をかくと血がドロドロになり流れが悪くなります。すると、筋肉に届く栄養がスムーズに届かないので適宜水分補給することも忘れずに。