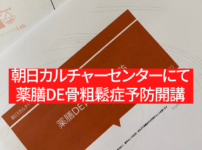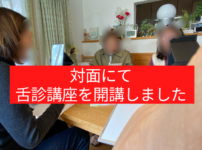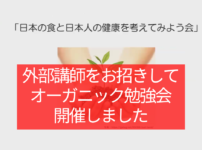疲れが溜まったり、睡眠不足になるとできやすい「ものもらい」。
ものもらいは関東の言い方で、関西圏では「めばちこ」、他の地域では「めいぼ」などと呼ばれる目の炎症です。
正確には、麦粒腫と言い細菌感染が原因ですが、似た症状の物に霰粒腫(さんりゅうしゅ)というものもあります。
どちらもまぶたの内側や、目のきわ、まつげの生え際などの炎症です。
しかし、この二つには原因の違いがあります。それぞれ炎症に変わりはありません。
何度も繰り返すようなら体質的な原因やよく食べているものが原因の事があります。
ここでは、それぞれについて食べると良いもの、止めた方が良いものについてお伝えします。
目次
いわゆる「ものもらい」麦粒腫の原因
いわゆる「ものもらい」麦粒腫の原因は細菌です。
疲労や睡眠不足で免疫力、抵抗力が落ちた時になりやすく抗生剤で治すことができるものになります。
中医学的に考えられる可能性は、
1.本来持っている防御機能が衰えた 2.防御機能より強い細菌の侵入 3.ストレスによる免疫機能の低下などが考えられます。
目に出ているので、五臓の肝が関わります。肝は体の構成要素である「血」を溜めているとされるため寝不足が続くと溜めている「血」の不足から陰陽バランスが崩れるのです。
「陽」は熱・熱い・火の性質を持ち「陰」は冷たい・冷やす、水の性質を持ち「血」が不足すると陰の成分が減り陽が強くなってしまいます。
そのため、目の縁やまぶたの内側の炎症と言う熱症状として現れるのです。
ものもらいと似ているが原因が違う霰粒腫とは
霰粒腫は、目が乾かないよう分泌される脂の分泌腺、マイボーム腺のつまりが原因です。
涙が乾かないようにその脂が目の表面を覆う役目をするそうです。
このマイボーム線がつまるということは、中医学的には体液が粘性を帯びていると考えられます。
まだ炎症に至っていなくても膨らみがあったりしこりになっていたら霰粒腫かもしれません。
炎症が起きていたら避けた方が良い食べ物
炎症とは、「炎」と言う字が表すように熱の症状なので、体を強く温める性質のある食材は避けるべきです。
例えば、唐辛子、生のにんにく、山椒、コショウ、シナモンなどのスパイス系、アルコール類など。
以前、喉が少しイガイガする時にキムチを食べて喉が痛くなった実体験があります。
炎症が起こりかかってる、もしくは炎症が起こるかもしれない時は食べると強くカラダを温める食材を止める方が無難でしょう。
また、「陽」は上に上がる性質を持ちます。炎症である熱は「陽」の性質なので陽のパワーを上にあげる食材も避ける方が良いですね。
例えば、コーヒー、チョコレート、ナッツ類です。
これらは、ニキビが悪化する原因となるものだけでなく、花粉症の鼻づまりや目のかゆみも悪化させるものです。
ものもらいができている時、できやすい人が日ごろから食べると良い食べ物
いわゆる「ものもらい」麦粒腫ができやすい人は、体の抵抗力=バリア機能を高める食べ物を食べることと、バリア機能は五臓の「肺」が関わるので「肺」の働きをアップさせることが重要です。
肺のバリア機能をアップさせる食べ物は、色で言うと白い食材になります。
例えば、山芋(長芋)、白きくらげ、ゆり根、梨など
陰の性質は水なので、乾燥に弱い「肺」を潤わせる意味で海の物がお勧めです。
イカ、帆立、牡蠣、あさり、はまぐり、ぶり、サヨリなど
体の構成要素「気血津液」の「血」の不足を補う食材も常に食べます。
黒豆・黒きくらげ・黒ごま。にんじん・ほうれん草・ヨモギ・なつめ・クコの実・牛の赤身・レバー・かつお・鮭・まぐろなど
ものもらいと似ている霰粒腫ができている時、できやすい人が日ごろから食べると良い食べ物
脂っこいもの、乳製品、砂糖を使ったもの、コッテリしたもの、アルコールを控えたうえで、海藻類やきのこ、お酢を使った料理、雑穀類、はと麦、黒豆、アスパラガス、クレソン、チシャなどを
たっぷり食べて下さい。
つまりが起きているということは、一時的にしろ要らない水分がドロドロになっていることを予想して体に熱を加えて、体液を乾燥させドロドロにしないようにすることも大切です。
やはりここでも、スパイス類は止めるべきでしょう。
まとめ
中医学的に見た特徴に合わせて食材を選ぶと、ものもらいに良い食べ物を食べるより、まずは避けるとよいものを先に止めた方が早く症状が変わることが多いです。
その上で、「血」を補いつつ五臓の「肺」をアップさせバリア機能を強くする食べ物を食べます。
要らない水分をドロドロにしないためにも、激辛料理や毎日続けて揚げ物を食べたり乳製品を摂ることを控え、水はけのよい体にしておくことを心がけましょう。
これから年末年始にかけて、アルコールを飲む機会も増えると思いますが、一緒に食べるおつまみや料理に気をつけるだけでも違います。
何事も腹八分目、毎日同じものを食べ続けるのは止めましょう。
【関連記事】